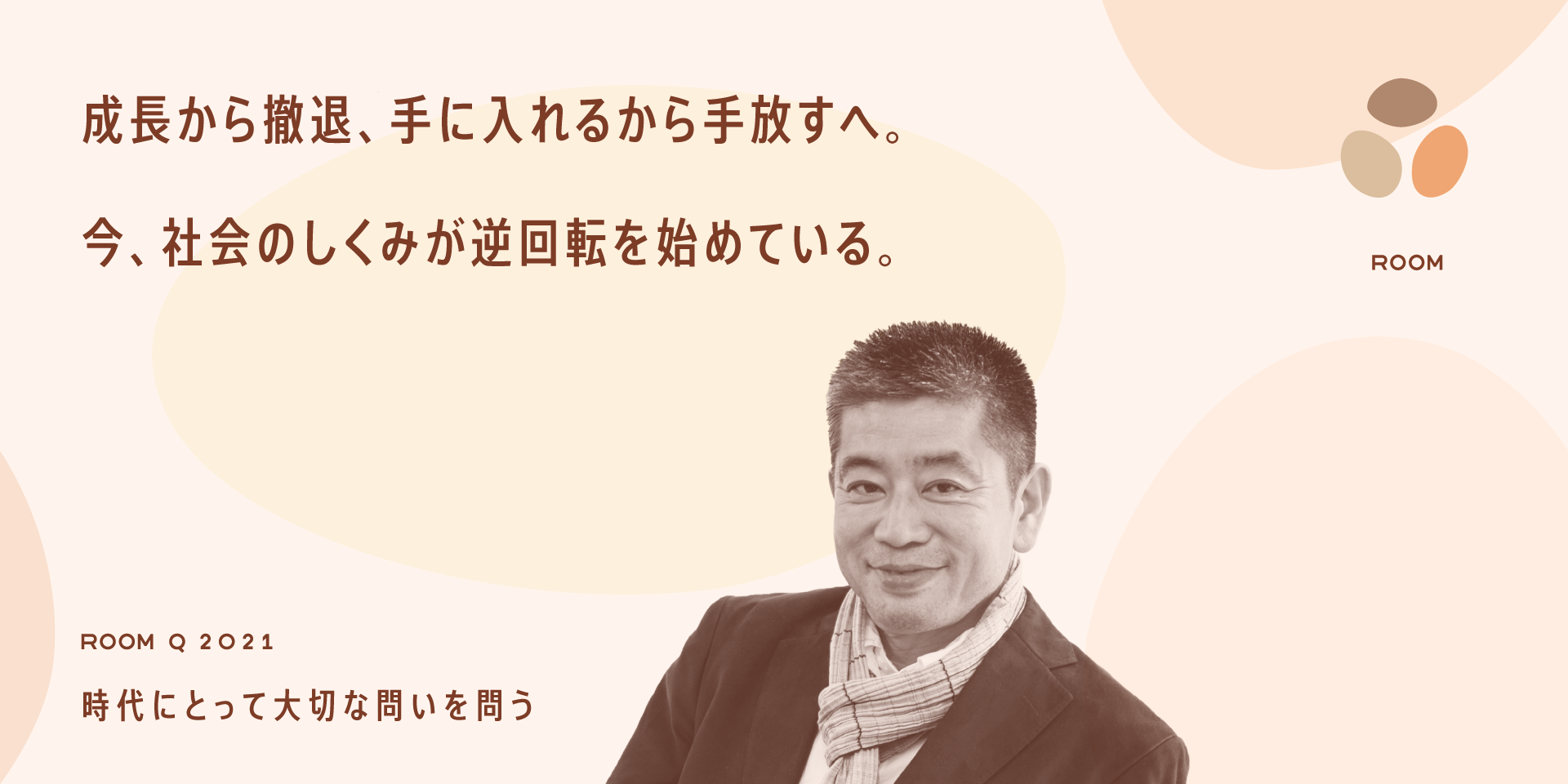テクノロジーの進化は「人と人のつながり」が鍵となるーーテクノロジーの未来と社会デザイン【ミラツクフォーラム2017】
ミラツクにゆかりのある多様な領域の方々をお招きし、一年の振り返りと総括を行う「ミラツク年次フォーラム」。今年は2017年12月23日、東京日本橋の「株式会社デンソー東京支社」にて開催されました。多くの参加者が会場を埋めるなか、多様な豪華ゲストによる計10本のセッションが行われ、1年を締めくくるにふさわしいイベントとなりました。
セッション3では、民間として宇宙ビジネスに取り組む石田真廉さん、「富士フイルム株式会社」でオープンイノベーションを推進する小島健嗣さん、「理化学研究所」で未来の研究開発構想に携わる山岸卓視さんのほか、コメンテーターとして、「名古屋商科大学ビジネススクール」教授・澤谷由里子が登壇。ミラツク西村の進行のもと、「テクノロジーの未来と社会デザイン」について語り合いました。新しいテクノロジーを社会に組み込み、より良い未来のために活用する方法について模索します。
(写真撮影:Lyie Nitta)
 この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
登壇者プロフィール
A.T.カーニー株式会社プリンシパル/一般社団法人SPACETIDE 代表理事
2003年 東京大学工学部卒。グローバルコンサルティングファーム「A.T. Kearney」にて宇宙業界、自動車業界、機械業界を中心に15年超の経営コンサルティング経験。「一般社団法人SPACETIDE」の共同創業者兼代表理事として、新たな民間宇宙ビジネス振興を目的に年次カンファレンス「SPACETIDE」を主催。「内閣府」宇宙政策委員会 宇宙民生利用部会委員。「科学技術振興機構 ImPACT(革新的研究開発推進プログラム)」アドバイザー。「ITmediaビジネスオンライン」にて「宇宙ビジネスの新潮流」を2014年より連載中。また著書に『宇宙ビジネス入門 Newspace革命の全貌』(日経BP社)。
富士フイルム株式会社 経営企画本部 イノベーション戦略企画部 Open Innovation Hub館長
千葉大学工学部工業意匠学科卒業後、電子機器メーカーを経て「富士フイルム」に入社。デザインセンターにて情報システム、理化学機器等のプロダクトデザインを担当。デザインに求められる時代の変化にあわせてインターフェースデザイン、デジタルコンテンツデザイン、ユーザビリティデザイン、ソリューションデザイン各グループを立ち上げる。2011年よりR&D統括本部技術戦略部で技術広報 およびオープンイノベーションを担当。共創による新規事業創出を加速支援する場を提案、2014年、「FUJIFILM Open Innovation Hub」開設。2015年3月より現職。神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科非常勤講師。
国立研究開発法人理化学研究所 経営企画部 企画課 兼 未来戦略室 副主幹
博士号取得後ポスドクとして研究に従事。2008年末より「知的財産戦略センター(当時)」にてiPS細胞に関する技術の権利化や実用化などに携わる。2012年からは「環境資源科学研究センター」の運営に携わり、研究企画、産業連携等の業務に従事。2016年3月より現職。主な業務は社会課題の解決に貢献するエンジニアリング研究の立上げ・推進、産業界と連携した新たな研究プロジェクトの立案など。また、JSTのプログラムマネージャー育成・活躍推進プログラムに参加中。
名古屋商科大学大学院マネジメント研究科ビジネススクール教授、Center for Entreprenuership, DIrector
/ミラツク アドバイザー
東京工業大学大学院総合理工学研究科システム科学専攻修了。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。「(株)日本IBM」入社。情報技術の研究開発、「IBM東京基礎研究所」にてサービス研究に従事。「科学技術振興機構サービス科学プログラム(S3FIRE)」フェロー、早稲田大学教授を経て、18年4月より現職。「経済産業省産業構造審議会地域経済産業分科会」委員、「攻めのIT投資評価指標策定委員会」委員、「早稲田大学ビジネススクール」非常勤講師、「早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構」客員上級研究員、「INFORMS Service Science」など兼務。主な著作『Global Perspectives on Service Science: Japan(共編著、Springer)』『Serviceology for Designing the Future(共編著、Springer)』『Handbook of Service Science Vol.2 (共編著、Springer)』など。
異分野の人々が出会い、共創するオープンな場をつくる
西村セッション3は「テクノロジーの未来と社会デザイン」をテーマに進めていきたいと思います。まずは自己紹介からスタートしましょうか。早速ですが、石田さんからお願いします。
石田さんこんばんは、石田です。宇宙ビジネスに携わっています。みなさんにはあまり馴染みのない領域だと思いますが、日本には現在、堀江貴文さんのロケット開発をはじめ、さまざまな宇宙ベンチャーが30社ほど存在しています。
僕の宇宙ビジネスへのアプローチは二つあります。一つ目は、3年前に立ち上げた「一般社団法人スペースタイド」での活動です。ここでは、日本初の宇宙ビジネスカンファレンスの運営を手がけています。政府関係者から民間企業、投資家まで、宇宙ビジネスに関わるステークホルダー全員が一堂に会する場を設け、新たな宇宙ビジネスを加速する産業横断のプラットフォームの構築を目指しています。
二つ目は、経営コンサルタントとして所属する「A.T.カーニー」での活動です。宇宙ビジネスを取り巻く環境は複雑性を増しており、政府の政策方針や企業の戦略意思決定には多種多様な課題が存在します。政府委員として、あるいはコンサルタントとして伴走しながら課題解決の支援をしていくのも僕の重要な業務の一つです。
小島さん「富士フイルム」の小島と申します。2014年、当社がミッドタウンに開設した「オープンイノベーションハブ」の館長を務めています。ここは「富士フイルム」の開発した技術を常設展示し、社外とのコミュニケーションを通じて新たな事業創出を目指す場となっています。
「富士フイルム」は、もともと写真フィルムのメーカーです。しかし最近は、化粧品メーカーだと思っている人も増えてきています。会社が大きく業態変革するきっかけとなった象徴的な事業ということで、注目を集めているのだと思います。
業態変革の背景には、写真フィルムの需要の激減があります。カラーフィルムの総需要は、2000年を100とすると今は5%未満です。そこで、これまで培ってきた技術やリソースを全て棚卸して、新しい事業を生み出す必要に迫られました。そのためには「富士フイルム」の技術をもとに、お客様の課題を一緒に解決していく場が必要です。そこで共創の場として「オープンイノベーションハブ」が誕生しました。
まだまだ課題はありますが、多様なお客様とのコミュニケーションを通じて、想定外のおもしろい出来事も起こりつつあります。今は具体的な成果を出すために日々頑張っているところです。
山岸さん「理化学研究所」(以下、理研)の山岸と申します。「理研」は、我が国唯一の基礎科学の総合研究所で、文科省傘下の研究開発法人です。3500人ほどが在籍しており、うち3000人ほどが研究者です。所属は経営企画部ですが、「理研」における経営企画とは、理研内の経営事項だけでなく、文科省と連携した国会対応や予算関連の手続きなどが主な業務です。私はなかでも“経営陣特命事項”のような案件を担当することが多く、理事長(元京都大学総長の松本紘氏)をはじめとする経営陣の要望に応えるのも大事な仕事です。
昨年9月に設置した「未来戦略室」もその一つです。ここでは、未来社会のビジョンづくりから具体的な研究プロジェクトの立案、実践までを目指しています。実は西村さんには、これらの活動をサポートするイノベーションデザイナー第1号に就任いただいています。このように、特命事項を含め、日々新しい研究プロジェクトを立ち上げて回しています。
澤谷さん澤谷といいます。もともとは「IBM研究所」でパーソナルシステムやサービス研究に従事していました。そこで、サービスを科学的に追求し、デザインするサービスサイエンスという新たな研究領域を立ち上げました。5年ほど前には、企業内にとどまらず、より研究を深化させるために大学に移りました。今日はどうぞよろしくお願いします。
テクノロジーの社会への実装を阻むものは何か?
西村今年はイノベーションデザイナー就任をきっかけに、「理研」の素晴らしい研究者の方々と出会う機会に恵まれた一年でした。「理研」には、非常に優秀で、しかも世の中への貢献意識も強い研究者が何千人も集まっています。一方で、これほどの人たちが揃っても、世の中はそれほど大きくは変化しません。僕はそれがずっと疑問で。科学技術やテクノロジーの進化を、もっとスムーズに社会に実装していくには、何が必要なのか。今日はこのあたりのテーマを深く掘り下げたいと思っています。
まずは石田さんに、新しいテクノロジーをビジネスに活用する際にボトルネックとなるポイントを伺いたいと思います。
石田さんまず、宇宙ビジネスは“国がやるもの”というイメージがありますよね。実際、日本なら「宇宙航空研究開発機構(JAXA)」、アメリカなら「アメリカ航空宇宙局(NASA)」、ヨーロッパなら「欧州宇宙機関(ESA)」という政府の宇宙機関があります。こうした国家機関が大規模なプロジェクトを主導するのが宇宙開発、という印象が強い。
この10年ほどで、民間主導の宇宙ビジネスに対する期待や可能性が拡大しつつありますが、それとともに環境整備が重要になっています。そこがボトルネックとなっている事例は少なくありません。
まずは法整備です。「そもそも宇宙ビジネスを民間がやってもいいのか?」「衛星を勝手に打ち上げてもいいのか」「ロケットをつくるのに許可は必要か」。これらの問題をクリアにし、誰もが安心して挑戦できる法制度がなければ、宇宙ビジネスの発展は望めません。日本では2016年に「宇宙二法」が成立し、宇宙ビジネス発展の土台が整いつつあります。
二つ目は、従来の宇宙開発にまつわる技術や人的リソースの大半を国や大手航空宇宙企業が所有しているという点。他方で、新しいテクノロジーやアイデアは必ずしも従来宇宙と関係のなかった企業が保有しているケースがあります。従って、産業振興や産業拡大へとつなげていくためには、従来宇宙をリードしてきた方々と新たな民間企業の連携が不可欠です。
これらを促進するためにも政策が重要です。重要なのは、宇宙ビジネスに関わる企業や投資家が、どんどん意見を言うこと。ロビー活動なしに政策はつくれません。
三つ目は、他のベンチャービジネスと同様、起業家にリスクマネーが必要になる点です。ただし、宇宙ビジネスに必要なコストは、ITベンチャーとは桁違いに大きい。シードファンディグでも数億、シリーズAなら数十億の調達は必須です。
先日、月面資源開発の事業化に取り組む「アイスペース」が101.5億円を調達し、日本のベンチャー史上、過去最高額だと話題になりました。出資者には、いわゆる政府系ファンドのほか、「TBS」や「コニカミノルタ」「スズキ」「電通」など民間企業10社が名を連ねています。
日本の宇宙開発の国家予算は3000億円程度しかありません。対するアメリカは4.5兆円です。従って民間のリスクマネーの流入が重要です。しかし、日本のVCの年間投資額は1500億円程度ですから、大手企業の参加が重要です。そういう大手企業がいかに宇宙ビジネスに関心を持って、市場に参入してくれるかが鍵になるのです。
西村ちなみに、宇宙ビジネスでは具体的にどういった事業展開が可能なのでしょうか?
石田さん大きく分けると6つのカテゴリーがあります。最もわかりやすいのがロケットでしょう。再利用できるロケット開発を行うアメリカの企業「スペースX」が有名ですね。
二つ目は、衛星をつくるビジネスです。従来の衛星は非常に大型で、重量もありましたが、最近は重さが50キログラム程度の小型衛星の開発が活発になっています。大きな衛星を一つ打ち上げるより、小型の衛星を多数打ち上げる方が故障などのリスクヘッジに備えられるためです。
三つ目は、衛星データを活用した事業です。例えば、GPS衛星のデータを利用した「グーグルマップ」「カーナビゲーション」、最近では「ポケモンGO」などが代表例です。
四つ目は、宇宙を研究の場として活用することです。すでに宇宙空間という特殊な環境下で、無重力や宇宙放射線などを利用したさまざまな科学実験が行われ、創薬や新素材の開発などに役立てられています。
五つ目は、宇宙旅行ビジネスです。この分野をリードするのが、イギリスの事業家リチャード・ブランソンが創業した「ヴァージン・ギャラクティック」、そして「アマゾン・ドット・コム」を創業したジェフ・ベゾス率いる「ブルー・オリジン」です。「ブルー・オリジン」は、2019年にもプロの飛行士を乗せたロケットを打ち上げる予定だそうで、宇宙旅行の商業化はいよいよ現実味を帯びてきています。
最後は、宇宙での資源開発です。我々が宇宙で活動するには、水や燃料をはじめ、膨大な資源が必要です。しかし、地球からわざわざ持参するには巨額のコストがかかります。もし、これらを宇宙で調達できれば、宇宙開発をさらに推進することが可能になります。先ほど紹介した「アイスペース」も、数年以内に月着陸船を打ち上げ、月面で水などの資源探査を行うと発表しています。
西村六つとも興味深いですね。ところで、先ほどの三つの課題についてもう少しお聞きしたいのですが、課題の一つである法整備は少しずつ整いつつある、と。それでも海外に比べて、日本の宇宙ビジネスが遅れている理由は何でしょうか?
石田さん端的に、時間が必要なんです。アメリカでは1980年代に「米国改正商業宇宙打上げ法 (商業打上げ法)」が制定されましたが、日本では2年前に「宇宙活動法」が制定されるまで、民間企業のロケット打ち上げに関する法律がありませんでした。従来は、民間企業がロケットを飛ばすなんて事態を想定していなかったからです。
法律というのは、既成の概念には当てはまらない新しいことをやりたい人が一定以上集まり、強い意志で法整備を望むロビー活動をして、ようやくつくられるもの。そういう意味で、どうしても時間が必要なんです。
一つ、象徴的な話があります。アメリカに、多額の賞金で最新テクノロジーによるアイデアを実現させるコンテストを多数開催してきた「X PRIZE 財団」という団体があります。創始者のピーター・ディアマンテスは、実にクレイジーな実業家で、1990年代に宇宙旅行を実現するための民間宇宙機コンテスト「X PRIZE CUP」の開始を宣言しました。有人の有翼機で、高度100キロメートルまで行って戻ってこられたら賞金10億円、というような内容です。2004年、ついにあるチームが成功するんですが、それがさっき紹介したリチャード・ブランソンなんです。
ピーター・ディアマンテスの凄いところは、当時二つの超難問を抱えていたにもかかわらず、コンテストを成功させたことです。一つは、優勝賞金に充てるお金が1円もなかったこと。もう一つは、法律上、100キロメートルの高度への有人飛行がカバーされていなかったことです。
彼の回顧録によれば、賞金の10億円を集めるために300社以上の企業を回ったとあります。また、法律の問題についても、ロビー活動をしまくって、なんと法律を作ってしまったんです。2003年から2004年にかけて、商業打ち上げ法が改正されたおかげで、結果的にコンテストを開催することができた。つまり、新しい産業の発展は、クレイジーなイノベーターをどれだけ多く集め、その熱量を高め、政界や世論も巻き込んで社会に流れをつくっていけるかにかかっているわけです。僕が続けているカンファレンスは、そういう流れをつくる一つの手法でもあるんです。
西村ここで山岸さんにお聞きしたいんですが、「理研」では農業や水産業などと業界横断的につながって、研究成果や技術を活用した新規ビジネス創出に取り組まれています。そういった取り組みを前に進める上で、現場ではどんな難しさを感じていますか?
山岸さん農業の話でいうと、「理研」には植物科学領域で世界レベルの研究者が集まっていて、被引用回数の高い論文数でも世界トップクラスの研究者たちが大勢います。でも、彼らは実験用の植物の扱いには長けているものの、必ずしも自分で家庭菜園をしたり、野菜を育てたりしている訳ではありません。
論文を書くためのツールとして植物は使いますが、実験用の植物と実際の作物には大きなギャップがある。つまり、論文重視のアカデミアの世界では、研究成果を社会に役立てたくても、それを実装する手段やネットワークがないケースが多いんです。だからこそ、そのような研究者たちの実情を理解しつつ、彼らをさまざまなビジネスの現場とつなぐ“ハブ”となる人材が必要なのです。ところが、実際にはそういう人材はなかなかいない。それが最大の問題ですね。
私はこれまで、その“ハブ”機能の強化を意識し業務に取り組んできました。例えば、「環境資源科学研究センター」をサポートしていた際は、農業系の展示会等に足を運び、シナジーのありそうな企業を探し、それら企業と研究者との技術マッチングを行いました。
また、「理研」のネットワークのなかのさまざまな研究分野の研究者たちを横につなげていくことで、問題の解決に向けて前進することがあります。例えば水産に関してサポートしたうなぎの完全養殖の事例では、完全養殖の技術としては確立されていても、稚仔魚の生残率の低さとコスト面がネックになり、事業化まではまだまだという課題がありました。そこで、理研の分析化学やゲノム科学の研究者らと農水省系の研究機関等とマッチングを行い、現在うなぎの稚仔魚が自然界で実際どのようなものを食べているのかなど、餌の分析をはじめさまざまな要素を見直し、課題解決に向けた取り組みを進めています。
澤谷さんニーズがあるのに、そういう人材が育たない理由の一つには、アカデミアにおける業績とビジネスインパクトの両立を求められる「理研」の研究者の評価基準があるのではないでしょうか。つまり、現状では、例えば「バイオインフォマティクス」のような新しい融合領域をつくり、果敢に挑戦した研究者はリスクもありますが評価も得て優位になります。ならば、先ほどの水産の話でいうと、「フィッシュエンジニア」のような新領域をつくってしまえばいいと思うんですね。そこに現場の研究者たちのモチベーションが向かう可能性はないんでしょうか。
山岸さん「理研」の組織構成上、難しい事情があります。なぜなら、「理研」の研究者の約8割が任期制だからです。「理研」では、国がある研究領域を設定し、専門の研究センターを設立し、任期制の研究者が配置される。そうなると、その研究領域の中でアカデミックポジションを獲得していくことに研究者たちのコミットメントが向かってしまう。それぞれの研究者が領域横断的なイノベーションに課題意識を持っていても、任期内で一定の成果を出すことを優先せざるを得ない。これは「理研」に限らず、日本のアカデミズムが抱える最大の問題だと思います。
西村課題が多い一方で、逆に研究成果が思わぬ方向でイノベーションを生んだ事例はあるんでしょうか。
山岸さん中村龍平さんという研究者のケースですね。彼は、深海の熱水噴出孔のような光の届かない場所で、地球内部のエネルギーと元素を使って生きる生物の研究を通して電気エネルギーで生きる「暗黒の生態系」を提唱しています。彼は人の細胞の様に化学エネルギーで生きる細胞の中にも、電子の状態を変えれば代謝に変化を起こせるものが存在する、と主張しています。
その彼が、水産関連の研究で画期的な提案をしました。沿岸の海底環境浄化の研究をしている水産研究・教育機構の研究者が、ヘドロ化した沿岸の黒い底泥を持ってきた際、中村が「この砂には酸化鉄が入っているから電気が通る。電気を通すことでそこにいる生物の機能を用いて底泥を浄化できるかも知れない」と助言したんです。結果的に、研究室レベルではありますが、底泥に電圧をかける事で、そこにいる生物の代謝を制御し、環境を自ら浄化できるような生態系に変えてしまった。一事例とはいえ、能力の突出した研究者と社会をつなげると、思いもよらないイノベーションが起きる可能性はたしかにあるかもしれません。
西村ちなみに、山岸さんはなぜ研究者からブリッジ役に転向されたんですか?
山岸さん同世代の研究者には、私よりも何倍も優秀な人たちがたくさんおり、研究者としてやっていくのは難しいと感じたからです。そこで、サイエンスと産業をつなげる立場を目指した結果、ニッチなところで活躍の場を与えられたという感じです。
西村小島さんはいかがですか。なぜ今のポジションに?
小島さん僕はもともとデザイナーとして、プロダクトデザインに携わっていました。ところが、2000年頃から写真フィルムの需要が激減する流れのなかで、当時の古森重隆社長(現・会長)がオープンイノベーションを標榜し、大胆な組織改変を実行したという経緯があります。要するにR&Dの人材を一つに集めて、コミュニケーションさせる方針に転換したんです。
当時の「富士フイルム」では、研究者はいかに高い技術を開発するかに血道を上げる一方、それらを新規事業に転用するという発想は皆無に近い状況でした。そんな状況で、お互いにコミュニケーションを取って新しいビジネスを生み出すためには、何らかの共通言語が必要です。そこで2004年、コミュニケーションの共通言語をつくるため、デザイナーの私が呼ばれたわけです。そこでは発想とコミュニケーションを促すことでワークウェイの変革を目指すデザインシンキングをベースとしたワークショップなどに取り組みました。
そんなある日、私は突然、産学連携と技術広報強化のために技術戦略部に異動させられました。私は産学連携特有の決まり切ったスキームに則るのではなく、新しい手法を考えました。かつてのワークショップの経験を生かし、本当の意味でお客様と会話ができ、適切な提案ができる研究者を育てる場として「オープンイノベーションハブ」の創設を提案したのです。きっかけは異動でしたが、そこでの経験を自分の役割だと自覚したことが、今につながっていると思っています。
西村「オープンイノベーションハブ」創設からの4年間で、非常に上手くいったコラボレーション事例について教えていただけますか?
小島さん私たちはまず、訪れたお客様のニーズに対して仮説を立て、さまざまなご案内をします。仮説通りだった場合は、スムーズに進むんですが、一方で短期的なビジネスで終わってしまうことも少なくない。逆に、やりとりを繰り返すなかで、お互いが想定していない部分で課題を解決できる可能性が見えてくると、高揚感がありますね。ビジネスという面からは、中長期で取り組む案件と、足元の収益につながる案件を両立できる企業とパートナーシップを築くことが重要ですね。
西村逆に、困難を感じるのはどのような部分でしょうか。
小島さんサイエンティストや研究職の人間は、過去の事例を検証し、前例に学びながら今起きている事象を理解しようとする「フォアキャスト型」が多勢です。一方、ずば抜けた想像力で、自分の能力やスキルを新規の領域に応用したり拡張したりするのが得意な天才肌もいますが、そういう「バックキャスト型」の人材は、非常に限られます。
今後の人材開発には、この「フォアキャスト型」をどう「バックキャスト型」に変えていくかが大きなポイントになるでしょう。だからこそ、その変化を手助けする橋渡し人材の需要も増しているのです。
西村山岸さんにもお聞きします。クライアントの課題に興味を持って、一緒におもしろがりながら解決に取り組んでくれる研究者もいますよね。そういう人に共通する特徴とは何でしょうか。
山岸さん先ほどお話ししたように、「理研」の研究者の場合は任期制の有無が大きなポイントになると思います。任期がなく、長期スパンでキャリアを考えられる人にはそういった余裕も生まれやすいでしょう。あとは本人の資質ですね。好奇心旺盛で、クライアントの課題を自分ごととして考えられる人には発見も多い。好奇心を起点に領域を自由に行き来できる、いわゆる「天然キャラ」をどう育てていくかは重要なテーマです。
テクノロジーと産業を接続する場とヒトの重要性
西村石田さんに伺いたいのですが、一つは宇宙ビジネスに取り組む人たちの共通点。もう一つは、業界のフィールドに閉じず、異分野との共創やイノベーションを起こすために努力していることは何か。
石田さん起業家に関していえば、2〜3パターンしかありません。宇宙に限らず、破壊的な変化を好む人。2000年頃に参入したアメリカの起業家たちの多くは、宇宙の民主化というテーマに惹かれ、それを追い求める人たちです。
もう一つは、国の課題ではなく人類共通の課題に興味がある人。宇宙起業家たちの話は、必ず「人類はどうあるべきか」というヒューマニティに根ざしているんです。決して国家を主語にして語ったりしない。
三つ目は、とにかく宇宙が好き、ということ。ただし、研究対象としての宇宙ではなく、『スターウォーズ』や『スタートレック』などの世界観を愛しているんです。彼らは映画や映像から得た強烈な原体験を通じて、宇宙に強い愛着を持っています。にもかかわらず、遅々として進まない宇宙開発にしびれを切らして、「俺がやってやる!」というマインドを持つに至った人たちが多い印象ですね。
宇宙ビジネスを考えるためには、宇宙産業の歴史を理解する必要があります。日本の宇宙産業は歴史的に科学技術や研究開発を軸に発展してきました。それが2008年の「宇宙基本法」が成立した際には、科学技術だけでなくて、安全保障と産業振興も加えた三本柱となりました。しかしながら産業振興といっても、従来は国が目標設定をしてきたところが大きいため、技術はあっても、新たなビジネスのアイデアが不足している。これは世界共通の課題といえます。
手っ取り早い解決法は、とにかくプレイヤーを増やすこと。宇宙ビジネスには前例や雛形が存在しないので、とにかく多くの人々が色々なアイデアを出して試行錯誤しながら閾値を下げていく必要がある。参入障壁を下げるということが、非常に重要なんですね。
僕の主催する宇宙カンファレンスでは、参加者およそ500名のうち、約4割が宇宙関連のバックグラウンドを持っている人たちで、残りの6割は宇宙ビジネスの未経験者です。経験者は、できることとできないことを明確にする。その上で、未経験者たちは前提知識がない故に自由な発想でアイデアを出せる。今ある技術を新しいビジネスに飛躍させるには、このハイブリッドを可能にする場の設定が欠かせないんです。
西村多様な人々がちょうどいいバランスで集まる場を、どうやって仕掛けてきたんでしょうか。
石田さんカンファレンスを立ち上げた2015年時点で、宇宙ビジネスには多数の先駆者たちがいました。とくにVCの方々は、時代を先読みするプロですから、すでに宇宙ビジネスに多数の投資を行い、大きな影響力を持っていた。例えば「インキュベイトファンド」の赤浦徹さんや「慶應イノベーション・イニシアティブ」CEOの山岸広太郎さん、「TomyK Ltd.」代表の鎌田富久さんなどですね。だから、彼らにアプローチして、一気に情報を拡散してもらったんです。
僕自身が語るのではなく、社会に影響力を持つ人たちに語ってもらう。ビジネスの主体である企業家の熱意を理解した上で、彼ら自身の言葉で、世の中にインフルエンスできる方々に仲間になってもらうこと。これがすごく大事なんです。
西村なるほど、大変興味深いです。最後に、みなさんにぜひ伺いたいのですが、どうしたら世界中に散らばる優れたテクノロジーを社会に実装し、進化させることができるのか。そのために必要なしくみや手法とは何か。ご意見をお願いします。
小島さん「オープンイノベーションハブ」の運営を通じて、お客様と研究者、企業をつなぐだけではなく、人を育てることの重要性を実感しています。そこで少しずつですが、人材教育も始めています。例えば、ベンチャー起業家を招いて、30代の中堅社員たちの前で話をしてもらう。スピーカーの情熱や夢を形にするプロセスを共有することで、目の前の業務に忙殺されがちな社員たちに「何を実現したいのか」を再確認してもらうんです。多様な価値観に触れ、刺激をもらうことで社員たちの覚醒を促す。そういう環境づくりが今、企業に強く求められていると思います。
山岸さん科学技術を社会に落とし込むために、私が貢献できることは、やはり「理研」のあらゆる領域の研究者たちと共に、横のつながりやコミュニティをしっかりつくることです。彼らがそれぞれの技術や専門知識を活かし、社会に役立つ形でアウトプットするには、彼らが共感できるビジョンが必要です。それは「もっとおいしい牛乳をつくりたい」とか「食べ物に困る人を減らしたい」といった身近なテーマでもいいんです。身近な課題への意識を共有したり、共感でつながれるコミュニティを大事に育てていくこと、そしてそういう場をマネジメントできる人材を増やしていくこと。それが一番重要なことだと思います。
澤谷さん今日、みなさんのお話を聞いて改めて感じたのは、やはりイノベーションは、「つながり」から生まれるものだということです。今日登壇された方はみな、「つなげる人」ですよね。誰かと誰かをつなげることで、新しい価値が生まれる。ただし、その成否の鍵は、私たち自身のなかにある制約や縛りが握っています。
でも私は、その制約を研究者自身に委ねてはいけないと思うんです。新しい事業や価値を生むために、好奇心であれこれ動くことは良いことですが、戦略的に動けたらもっと効率よくできることもある。再現性のある形でノウハウを伝えることもできる。
実はこれって、本来はマネージャーの役目なんです。企業は、そういう「つなげる」スキルを持ったマネージャー人材を確保するべきでしょう。研究者には研究者本来の役割に集中できる環境をつくることも大事です。そうすれば、世界中の有益な研究活動は、もっとスムーズに社会に還元されていくのではないでしょうか。
西村それでは「テクノロジーの未来と社会デザイン」のセッションはここまでにしたいと思います。改めまして、石田さん、小島さん、山岸さん、そして澤谷先生、本日はありがとうございました。
 この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
ROOMの登録:http://room.emerging-future.org/
ROOMの背景:https://note.com/miratuku/n/nd430ea674a7f