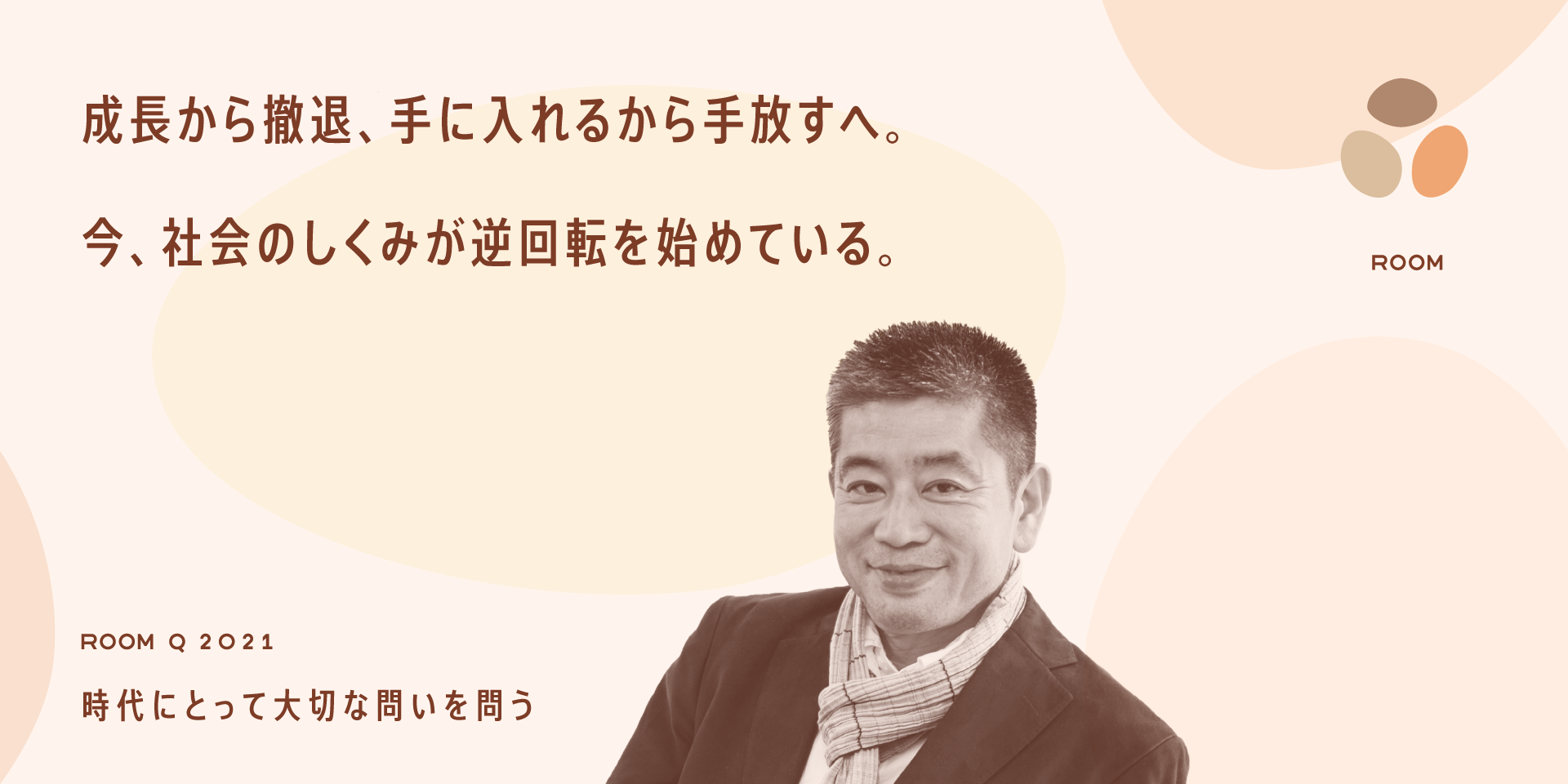未来社会デザインとソーシャル・イノベーション。「I」が未来を切り拓き、「間」からイノベーションが生まれる【ミラツクフォーラム2018】

ミラツクと親交の深いオピニオンリーダーや企業関係者が集結し、白熱の議論を繰り広げる年の瀬の恒例イベント「ミラツク年次フォーラム」。2018年は舞台を東京の新名所としてオープンした「東京ミッドタウン日比谷」に移し、12月23日に開催しました。
今回も、「未来社会」「ソーシャル・イノベーション」「人材育成」「まち」などをテーマに熱いトークを展開。そのオープニングを飾る基調鼎談に登場したのが、「INNO LAB International」co-founderの井上英之さんと、「京都市ソーシャル・イノベーション研究所」所長の大室悦賀さんです。テーマは、「未来社会デザインとソーシャル・イノベーション」。幅広い知見とユーモア溢れる発想をもつ2人の掛け合いは、果たしてどこで着地したのでしょうか。ミラツク代表・西村の進行で行った対談の様子をレポートします。
 この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
登壇者プロフィール
INNO LAB International co-founder / NPO法人ミラツク アドバイザー
2001年から、NPO法人「ETIC.」にて、日本初のソーシャルベンチャー向けプランコンテスト「STYLE」を開催するなど、若い社会起業家の育成・輩出に取り組む。2003年、NPOや社会起業にビジネスパーソンのお金と専門性を生かした時間の投資をする、「ソーシャルベンチャー・パートナーズ(SVP)東京」を設立。2005年より、慶応大学SFCにて「社会起業論」などの、ソーシャル・イノベーション系授業群を開発。「マイプロジェクト」と呼ばれるプロジェクト型の手法は、高校から社会人まで広がっている。2012~14年、米国スタンフォード大学、クレアモント大学院大学に客員研究員として滞在した。近年は、マインドフルネスとソーシャル・イノベーションを組み合わせたリーダーシップ開発に取り組む。
京都市ソーシャル・イノベーション研究所 所長 / NPO法人ミラツク アドバイザー
1961年、東京都生まれ。「株式会社サンフードジャパン」、東京都府中市庁への勤務を経て、2015年4月より、京都産業大学経営学部教授に就任。著書に、『サステイナブル・カンパニー入門』『ソーシャル・イノベーション』『ソーシャル・ビジネス:地域の課題をビジネスで解決する』『ケースに学ぶソーシャル・マネジメント』『ソーシャル・ エンタープライズ』『NPOと事業』などがある。社会的課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・ビジネスをベースに、NPOなどのサードセクター、企業セクター、行政セクターの3つのセクターを研究対象として、全国各地を飛び回り、アドバイスや講演を行っている。2018年4月から、長野県立大学(長野市)教授兼ソーシャル・イノベーション創出センター長。
新しい未来。その「見方」はあるのか
西村「ミラツク」で未来予測のリサーチなどをしていると、「未来の話なんて、そもそも当たるの?」なんて言われることがあります。でも、私は当たるかどうかにそれほど興味はありません。
「可能性がある」「自分がやりたい」と思えばやればいいし、やりたくなかったらやらなければいい。それが「未来」だと思うんです。ただ、そうはいっても、ただ漠然と未来のことを考えているだけではもったいない。もう少し、こういう風に未来のことを考えてみたら、おもしろいかもしれない。こういう視点で考えると、新たな可能性が見えてくる。今日は、そんな風に未来の「見方」を言語化できるような話をしたいと思っています。さて、まずは2人の自己紹介から始めましょうか。
大室さん初めまして、大室です。今は主に長野県立大学で2018年4月に開設された「ソーシャル・イノベーション創出センター」に勤務しています。全国からさまざまなプロフェッショナルを招聘し、産学官で連携しながら地域課題の解決を目指しています。東京と長野の2拠点生活を送っています。
今最も興味があるのは、経済も経営もすべて、もう一度哲学、つまり根底のところに戻らないと解き明かせない世界になってきている、ということです。これまでの西洋的な哲学では解を出せない社会になってきています。東洋的な哲学で世界を紐解いてみたい。それが最近の関心事です。
井上さん私は、社会起業やソーシャル・イノベーションという分野をつくることを通じて、新たな個人や仕事のあり方、そして関係性を生み出すことに取り組んできました。特に、日本のビジネスパーソンたちがもつ経験やスキル、情熱を活かせれば、個人も社会ももっとハッピーになるのではないか。その流れや仕組みをつくれないかと思って、まずは「NPO法人ETIC.」と一緒に20〜30代を対象にしたソーシャル・ベンチャー向けのビジネスプランコンテストを始めました。
そして、次に立ち上げたのが「ソーシャルベンチャー・パートナーズ(SVP)東京」です。革新的なNPOや社会変化を目的とした事業に、ビジネスパーソンたちがお金を出し、さらに自分の専門性を生かしてコミットする、という仕組みを提供する団体です。こうした活動を通じて、この社会の立場の違う人たちがつながり出したときに、予想していなかったような変化や新たな流れが生まれ、新しい未来が見えてくる。そんな現象をいくつも見てきました。
西村井上さんは、最近の関心事は何かありますか。
井上さん今ふっと浮かんできたのは、「休みたい」ですね。3年ほど前、結婚8年目にして第一子が生まれたんです。ちょうどその頃、親族の介護が必要となり、また、親族の会社の承継問題に私たち夫婦で取り組まないといけない状況に直面しました。育児と介護、事業承継。これがまとめて身に降りかかってきました。「ほしい未来が何なのか」を繰り返し問い続け、その場その場でギリギリの選択と行動をしてきました。大切にしてきた、自分の本業を1〜2割程度にセーブしてきましたが、ようやく3年ほどかかって、つい数週間前にすべてがクローズしました。
クローズした直後にビルを出て、ふと空を見たら、あまりに広く感じて驚きました。荷物を下ろしてみて初めて、その重さに気がついたというか。ああ、しんどかったんだな、って。気づけばリアルに視野が狭くなっていたことに、ハッとしました。その直後は、逆に、副交感神経系が優位になりすぎたのか、体調がひどく悪化していました。
今は、いろいろとセルフケアをして、だいぶ元気になってきたところです。ですから、来年(2019年)は絵を描くでも、音楽をはじめるでも、歌舞伎役者になる(笑)でもいいんですが、一度リセットして、そのときに何が出てくるか。過去の延長上ではない未来を見てみたいと思っています。そういう意味で、「休みたい」と言いました。
経験や技術を脇に置いたまま、思考できるかどうか
西村井上さんのように、「これをやる」と決めて取り掛かるのではなく、「休む」という空白をつくることも大事な選択ですよね。このセッションのテーマである「未来社会とソーシャル・イノベーション」と、何か接点や関係性はありそうでしょうか。
大室さん基本的に私たちは、過去の思考や経験をすべて知らないうちにどんどん積み上げていく状況があると思います。無意識のうちに、どんどん積み上げているんです。そうすると、企業の人たちと話していて感じるのは、「0」から「1」をつくろうとしているのに、どうも「100」から「1」をつくろうとしているんですよ。過去の積み上げや経験を全部そのまま残したうえで「1」をつくろうとするから、結局つくれないんですよね。「うちの会社はこうあるべき」とか「こういう歴史がある」とか、あるいは合理性とか、そういうものをすべて背負ったかたちで「1」をつくろうとすること自体に、無理があります。
さきほどの井上さんの話ですが、目の前の課題に真正面から向き合うほど、次第に視野が狭くなっていきます。「事業継承しなければいけない」とそれがマストになると、「0」にならないから難しい問題がどんどん見えてきてしまう。その狭くなっていく視野をどう広げるかがポイントです。
最近、はまっている本があります。マルクス・ガブリエルという哲学者が書いた『なぜ世界は存在しないのか』です。人間はどんなに多くの人が集まっても、世界全土を捉えることはできない。それは結果として、世界は存在しないというような話です。私たちは特定の角度からモノを見てしまうから、ある一定の部分からしか世界を捉えることができないのです。
ですから、「可能性のある未来」を描くには、一度脇に置けるかどうかが重要です。大企業の人もそうですが、自分の技術を一度脇に置けるか置けないかが、大事なキーワードだと思います。決して「捨てる」のではありません。脇に置いたまま、思考できるかどうかです。
西村「違うことを考えよう」と言っても、脇に置いていない視点だとダメなわけですね。脇に置けるかどうか。その結果として、全く違うものが出てくるかもしれません。「ある状態」と「ない状態」で、思考を行ったり来たりできるかどうか、という話ですね。
大室さんそれと、外に開くことも大事ですよね。例えば、「可能性のある未来」に対して「確実性の高い未来」と言った瞬間に、それはステークホルダーに限定されます。でも、「可能性のある未来」と言えば、極端ですが誰でもいいわけですね。歌舞伎役者でも、お坊さんでも、神父さんでも。「確実性のある未来」を考えようとすると、そういう専門家が集まり始めます。オープンイノベーションのフィールドは、(会場を指して)こういう閉ざされた空間ではなく、町のようなもっとオープンな場であるべきだと思うんです。
イノベーションは「中心」ではなく「周辺」から起きる
井上さん一方で、あらゆる生物は「ニッチ」で育ちます。特定の環境や状況に適合して、生き残るために強みに特化し、その結果、鳥は空を飛ぶようになったりします。特定の戦略を取ることで、生存できる。同じように、ある特定の状況下において、僕たち人間も特化して、集団的な生物としての強みを持って生存してきたし、ネイティブ・アメリカンも特定の厳しい自然環境下で生きる術を持っていたから、何千年も特定のライフスタイルを維持したまま生き残ってきました。
そのように、「ニッチ」という、目の前の特定の条件の下で、すべてにおいて強いのではなく、特定の範囲において強いように進化し、生存し、今のかたちがあるんですよね。大室さんが言ったオープンイノベーションの戦略と、生存のためのニッチの戦略。このつながりや関連性も気になるところですね。
西村猿の話をしていいですか。アフリカのサバンナで、強い猿は森に残れて、弱い猿は森から追い出されたという話です。追い出された猿は、どうやって生きていくか。そこでとった戦略が、森の木にぶら下がるために培った「つかむ」力を使って、外からモノを持って帰ってくることでした。森の近くに子どもを隠しておいて、親が餌をとって持って帰ってくる。そういう生き延びる方法をもったと言われています。もともとは木にぶら下がるために培った「つかむ」という能力ですが、追い出された瞬間に別の使い方を発見したんです。
井上さんつまり、森を追い出されてニッチな特殊環境が生じ、そこでの生存のために、自分の特定の能力を伸ばした結果、「つかむ」を応用した新しい技術が生まれたわけですね。そうすると、今度は、その「つかむ」技術を他の場所に行って応用するとか、また違った人たちとのコラボも出来るようになりますね。
要は、オープンイノベーションといっても、一定の期間に、特定の環境や状況に限定したなかで特定の技能を磨いた人や技能集団がいて……例えば、そんな企業が、社外の専門家やデザイナー、音楽家など立場の異なるプレイヤーと「一緒に何かできないか」と開いたときに、新しい発想やアクションが出てくる、ということなのかなと、今、思いました。
大室さんイノベーションは「中心」からは起きないんですよ。すべて、「周辺」から起きるんです。私たちは日々、すべてロジックで説明できてしまう空間に囲まれています。だから「説明しなさい」とか「きっちりやらなければいけない」などと、いつも何かに攻め立てられているような感覚に襲われます。
誰も説明できていない空間。言い換えると、これがニッチな空間ですよね。実は、イノベーションの源泉はそこにあります。何か定義されておらず、誰も住んでいないような領域に出ていくことで、その環境に適応して、そこで「つかむ」力を備えるようになる。そういうニッチな領域のなかでも、どこか安心できる空間を探さないと、私たちは成長することができない。つまり、イノベーションを起こすためにオープンにするんだけど、そこには必ず安定したものと、誰もまだ説明できない領域が常に共存している。そこは必ず対(つい)の関係なんじゃないですか。
西村どこに空白があるのか。それを見つけるのは難しいですよね。自分たちが「ここまでだ」と認識している世界のなかで空白を探すのは簡単だけど、そうではない、認識していな場所を想像するにはどうしたらいいのでしょうか。
大室さんまず、空白やスペース、間は、モノが存在しないとそこに描くことはできないですよね。非常におもしろい視点があります。西洋的にみると「人」、東洋的にみると「人間」なんですよ。この違いは、興味深い。東洋的には、「間」が常に存在するわけです。
身近な例で言うと、二足歩行ロボットの「アシモ」。あれは、『鉄腕アトム』を見た人たちがそれをつくりたいと思って完成させたんです。最近では、ベンチャーの日本環境設計が映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』で描かれたゴミをエネルギーにして動く「デロリアン」を走行させました。石油由来のガソリンではない車を走らせた途端に、そこで新たな可能性が認識され、社会が劇的に変わっていくわけです。
映画『ジュラシック・パーク』が公開されて恐竜博物館が様変わりしたり、『銀河鉄道999(スリーナイン)』が出てきて宇宙への関心が一気に広がったのも同じことですね。つまり、まず空間をつくる作業が、イノベーションにおいてはとても重要です。その手段の1つが、「未来を想像する」ということ。それによって、曖昧な世界が生まれます。そのうえで、まずはその曖昧な世界を意図的につくる。さらに、その曖昧な世界の空間のなかに、今度は絵を描く人たちが必要になってきます。
今、ヨーロッパとアメリカでは「MBA」(Master of Business Administration=経営学修士)がどんどん衰退していて、代わりに「MFA」(Master of Fine Arts=美術学修士)が増えています。ビジネスとアートが、対等に議論されるようになってきているんです。その掛け算が次のビジネスを生み出すということで、アートシンキングという言葉と概念も広がっています。なぜなのか。それは、アートになった瞬間に、従来のロジックから外れていくことができるからです。
生物学者の福岡伸一さんが書いた『芸術と科学のあいだ』という本があります。この本で福岡さんは、実は科学よりも、アート(芸術)が下手すると何百年も先行しているのではないか、と分析しているんです。例えば、縄文土器や花が咲くメカニズムなど、のちに科学的に解明された事象も、昔の人々からみれば自然的なもの。論理的には解明できないけど、現象としてはすでにそこで起きている、と。今アートが世界的に注目されているのは、空白やスペースを使って、それをどうビジネス化していくか。その答えの1つが、あるからだと思います。
ビジネスとアートの“意外”な関係
西村研究者にインタビューして話を聞いていると、彼らは「何がわからないのか。それがわかればすごい研究ができる」と言うんです。「誰もまだやっていないかもしれない」ということを見つけさえすれば、そこに説明をつけていくことで新しい研究になる、と。その「やっていないかもしれない」を見つけられれば、新しい領域を切り開ける可能性があるわけです。
それと、ある研究者は「わけのわからない人がおもしろい」とも言っていました。そこで思ったのが、その「わけのわからなさ」が世の中の評価軸になるとおもしろうそうだな、ということです。今の世の中は、事あるごとに「説明してください」と求められ、理解できないものは評価されないことだらけのように見えます。
大室さんおそらく大企業などにいる人は強く感じていることだと思いますが、わからないことを楽しめるようなユニークな連中が今、どんどん企業からいなくなっている現実がありますよね。ベンチャーに行ったり、起業したり、あるいは地域のなかに入っていったり。そういう現象が起こっていて、これからどんどん加速していくんじゃないですか。そういう若い世代が、明らかに増えてますよね。
西村この前知り合いから、新しいプロジェクトの内容を聞いたんですが、久しぶりに本当に理解不能な内容だったんです。その場では全く理解できなかったけど、なんとか共感だけはしようと思って。でも時間が経つと、もしかしたらそこから何か新しいコミュニケーションが生まれて、社会がガラッと変わるかもしれない。一周回って、とてもおもしろいプロジェクトだと思うようになりました。
大室さん「共有」じゃなくて「共感」だと思うんですよね、今の時代は。感性の部分で、共感することが大事なキーワードだと思います。ただ、その感性も「0」にできない人が多いですよ。自分のなかに暗黙のロジックがあって、そのうえで感性を働かそうとする。それでは、本当の感性には届きません。自分の感性さえも疑い、思考フレームを外してあげないと、共感は働きません。そうすると、イノベーションのチャンスが生まれない。自分は直感だと思っていても、実は完全にロジックに支配されていて、直感だと思い込んでいるだけの状態の人が多いと思います。
アートの話に戻りますが、僕がよく知っているベンチャーの経営者たちは今、アートのオークションに熱中しています。要は、自分の感性を疑うことを、絵に求めているんです。それによって、自分の感性を磨く。言い方を変えると、自分の無意識の思考フレームを外す作業を、アートを通して行っているんです。
井上さん左脳を使ってギリギリまで仕事をしている人ほど、アートに興味をもちますよね。結果を出そうと追及すれば、やっぱりこういうテーマに至ると、僕も思います。
大室さんが話していたアートとビジネスの関係性でいうと、経営思想家ピーター・ドラッカーがつくったビジネススクールで行われた、ある授業の話を紹介したいと思います。その授業は、近隣にある、世界的に知られるデザインスクールとのコラボで、両校の学生たちがチームを組んで、出されたお題について一緒に議論し、一学期かけて新しいプロダクトの提案をするというものです。
でも、最初は全然うまくいかないんですね。デザインスクールの学生は時間に対して自由で、一方のビジネススクールの学生はミーティングの時間も管理して、早く帰りたい。時間の使い方だけでなく、ものごとの進め方も違います。スライドだって、ビジュアル的なデザインスクールの学生に対して、ビジネススクールの学生は数字と論理が中心です。ふだん意識していない前提が、だいぶ違うということに次第に気づき始め、かみ合わないまま発表するチームもありますが、これがうまくまわると、驚くような新しい作品が出来上がります。
では、私たちの「知」や「知っている」と認識していることは、どういう領域で成り立っているのか?一つめの領域は「I know I know」、つまり「私は何を知っているかを『知っている』」。次に「I know I don’t know」、こちらは「何を知らないかを『知っている』」ということですね。「会計ならわかるけど、法律は詳しくないよ」とか。
ただ、これって、ぼくたちの「知」のほんの一部で、残りの広大な領域は「I don’t know I don’t know」、つまり「何を知らないかを『知らない』」んですよね。多くの「知らない」は、知らないことも気づいていません。この授業を通じて、学生たちは、この「I don’t know I don’t know」の領域(=知らないと『知らなかった』ことに、気づく)に出合い、意識してこなかった自分や他者に出会い、そこから、新しい組み合わせからの発想や、今までになかった選択肢を生み出す機会にします。
さらには、僕たちの日常の意思決定のほとんどは、「無意識」で行われているといわれています。脳は意識的に行動した気になっているけど、実は体が先に勝手に動いていて、意識はその後から認識している。そうでないと、例えば、ピッチャーが投げた160キロの球を打つことはできないそうです。ピッチャーが160キロの球を投げてからベースに到達するまでのスピードは、脳が指示を出して体が動くよりも早いらしい。でも、打てる人がいる。これは、これまで「ボールを打つ」というパターンを繰り返してきたことを背景に、体が無意識的に対応している。無意識の「知」で対応していたんですね。
このように、意識できていない、つまり「知らない」けれども、無意識的にやっている良いプラクティスが僕らの中にある。「I don’t know I know」(私は知っていると「知らない」)と言うんでしょうか。意識していないけど、出来ている。その無意識の良いプラクティスに気づき、意識化し、パターン化することによって、今度は、意図して、より良い結果や新しい未来を生み出していける、と思っています。
「I」がなければ、「We」に行けない
井上さんあともう1つ、ぜひ紹介したいエピソードがあります。1カ月ほど前、米国の著名な経営学者であるピーター・センゲさんたちと十数人で、ネイティブ・アメリカンの聖地の森に入って二泊三日のキャンプをしてきたんです。「ソロ・キャンプ」と言うのですが、森の中に自分のテントを張り、それぞれが限られた別のエリアで3日間を独りで過ごします。その間、ファスティング(断食)もします。水にライムとレモン、メープルシロップなどを入れて、それを飲むだけで過ごすのですが、体や意識を浄化する作用もあるらしく、不思議とあまりお腹は空きません。また、時間が経つにつれて、段々と意識や身体感覚が冴えてくる感覚に出合っていくんです。
世界が自分に近づいてくる感じというのかな。その聖地の森には、岩やピンク色がかったたくさんの小石、サボテン、その他の木々がたくさんあるんですが、最初は、全体がぼんやりとしか見えていないんです。それが、次第に「あのサボテンとこのサボテンは同じ種類だけど、それぞれにこんな違いがある」とか、松の木や石ごとの個性など、それぞれの違いが浮き立ち、とてもにぎやかに飛び込んでくるんです。気づいたら、いつの間にか木や石たちにぶつぶつ話しかけていたり(笑)。
そうやって、個々が美しく浮き立ち、自分とつながりはじめたときに、世界の見え方が変わってくる。「私はあの石であり、同時に、あの石は私である」といったような、テントの前に座り、細部を見ながらその自分を俯瞰もしているような、不思議な主語が出現してくるような感覚が生まれてくるんです。「私」という主語が、しっかりここにあるんだけど、自然な感じで「We」にもつながっているというか。
夜になると、周囲からいろんな音が聞こえてきます。最初は、一つひとつの音に体がビクッと反応もします。熊がいるって、さんざん聞かされていたし(笑)。それが、暗さにも慣れてきて、だんだん自分の知覚の画素数も高くなってくると「ああ、この音は風にテントがなびいた音で、この音は木々が揺れてるんだよね」といった具合に、ほどよい緊張と緩みにシフトしながら、その時間や空間がクリアになってくるんです。
そうやって、世界の見え方や感じ方が変わってくると、いろんなリソースが見え始めてきます。今だって、この会場にある壁や椅子も含めて、すべての物理的な現象は誰かの手によって、自然にあった何かが加工され運ばれ、その結果、きっと必然としてここにある。一つひとつのモノや、一人ひとりが多様に浮き立っていて、同時につながっている。すべて世界がここにある。そんな感覚になってきます。
西村なんだか不思議で、興味深い話ですね……。
井上さんそのプログラムには家族と一緒に行ったんですが、子どもの寝かしつけや授乳もあるので、毎晩、妻は、キャンプを出て、子どものいる近くの宿舎に戻ることにしていました。彼女を車で送るために、僕もキャンプを出てその宿舎に行くと、いつもの世界が待っています。そして、ライトが付いている部屋に入った瞬間に、一気にモードが切り替わるんです。
何もないはずの森の中で、あんなに充実した時間を過ごしていたのに、急になぜか手持ち無沙汰に感じられて、刺激をほしがっている。情報と食べ物は、これ以上ない刺激のようです。必要もないのに、携帯で野球のニュースを探そうとしたり、ファスティング中なのに、食べ物を食べようとする。そんな自分に気づいた時、びっくりしました。あれれー!!、って。
つまり、私たちのマインドは、日常においては、このようにさまざまな情報や関係性などによって遮断され、あっちこっちを行き来しているんですよね。「つくりたい未来」「ほしい未来」など言いますが、それは、どのくらい自分のものなんだろうか?外側からの刺激への反応に過ぎなかったり、「みんな」が設定してるものに、実は合わせるように描いてはいないだろうか。もちろん、外側の影響はうけると思います。ただ、いったんそういうものを横において、自分の夢や目標が、本当にオーセンティック(本物)なものなのか。それがわからなくなっていることは、誰にも起きていると思います。
僕は企業研修や大学の授業では、初回はだいたいアートワークをやるんです。例えば、自分の人生を、川に例えた簡単な絵やコラージュを描いてもらいます。雑誌を切り抜いた写真など、選んで貼ってみたものを通じて、体感している気になることや、わくわくすること、エネルギーを感じることが浮かび上がってくる。そんな体感的な情報を観察して、自分のインテンション(意図)や「ほしい未来」に気づいていくことができます。
文字情報だけで自己分析しこの先を計画するよりも、はるかに広い情報源になるんですよね。「あ、こんなことが気になっているんだ~、私は」とか、「あー、そうだよね、これかなえたいよね」とか。自分の中から生まれたものに出合い、観察し、その上で、それを叶えるためにしたいことや、身の回りにある環境の使い方など、自分のプロジェクトを考え始めます。
今日のセッションのお題である「未来」を考えるときに、もしかすると非常にシンプルに、例えば子どもと森の中で遊ぶように、田植えの作業をするように、フィジカルに、体感的な何かをすることが、ヒントになるのではないでしょうか?その瞬間瞬間における自分の反応や変化、ワクワク感や違和感、体感することからの情報は大切だと思います。思考だけでなく、体や感情も含めた総合的な自分の中にある情報に、注意を向けてみる。いったん、いろんなものを手放したときに、自分の奥からもりもりと盛り上がってくる何かって、誰しも必ずあるはずです。
大室さんとても素敵な話ですね。主・客という従来の制度的な発想から脱することに意味があるということですね。今、西洋社会が自分たちの思想を疑問視して、次の段階に動いている事実があります。私たち日本人は「人間」という言葉が指すように、もともと「自」と「他」をわけない東洋的な発想でできています。ですから、ここでもう一度そこに戻りましょうよ。要は、自分と他人はわけない、自分と自然はわけない。わけているところから、イノベーションは生めないですよ。「間」にある空間を、どうつくるかが問われています。
井上さんソーシャル・イノベーションの分野では、よく「I・We・It」という言い方をします。円の真ん中に「I」(=私)があり、その周りに「We」(=私たち)、円の一番外側に「It」(=世の中)を書きます。要は、「Starting from I」(「私」から始める)なんですよね。日本では何かと、発想を「We」から始めてしまうことが多い。
我々は・・・って。すると、「I」が溶けてしまうんです。それぞれの「私」が何を感じているのか、何をしたいと思っているのか、どんな気持ちなのか。それを横において、いきなり当事者がはっきりしないままの「We」から、例えば会議を始めてしまう。すると、だんだん自分がなぜここにいるのかぼんやりしてしまう。チームのそれぞれの「I」につながっていない。商品や企画としてはOKでも、実は、本当には共感できていない。ロジックは通っているから企画は通るけど、それが同じように顧客の「I」にも届かず、売れない。
だから、「I」から始める。特にソーシャル・イノベーションのような社会に訴求しようとする分野では、これは重要なことなんです。「I」があるから、他の人の「I」に通ずる代表性がそこにあり、「We」の領域に行くことができる。そして、それが本質的なものであれば、より広い、深いインパクトとしての「It」にたどり着くことができます。「It」は、世の中やそれを動かすシステムのことですね。中学英語でやった、「It rains」とか、「It’s five o’clock」の「It」ですね。その、世の中のシステムや、普遍的なあり方そのものを変えていくところに届けるには、「I」から始まることが大切なんですね。
では、「I」にどうアクセスしていくのか。それは「I」だけを見つめて、ひたすら自己分析を続けるだけでは、なかなか届かない。自分に注意を向けつつ、「他」との関わりによって浮かび上がってきます。ビジネススクールの学生がデザインスクールの学生と交流する。3日間、森のなかでキャンプする。自分を受容し、異質なものにも開いていく中で、この世界にある「I don’t know I don’t know」も含めた、認識しきれていない自分自身や、自分以外のものが豊かに存在することに気づきはじめる。そこから、新しい未来が見えてくるのではないでしょうか。
西村ありがとうございます。腑に落ちました。このあたりで基調鼎談を終えたいと思います。井上さん、大室さん、貴重なお話をありがとうございました。
 この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
ROOMの登録:http://room.emerging-future.org/
ROOMの背景:https://note.com/miratuku/n/nd430ea674a7f