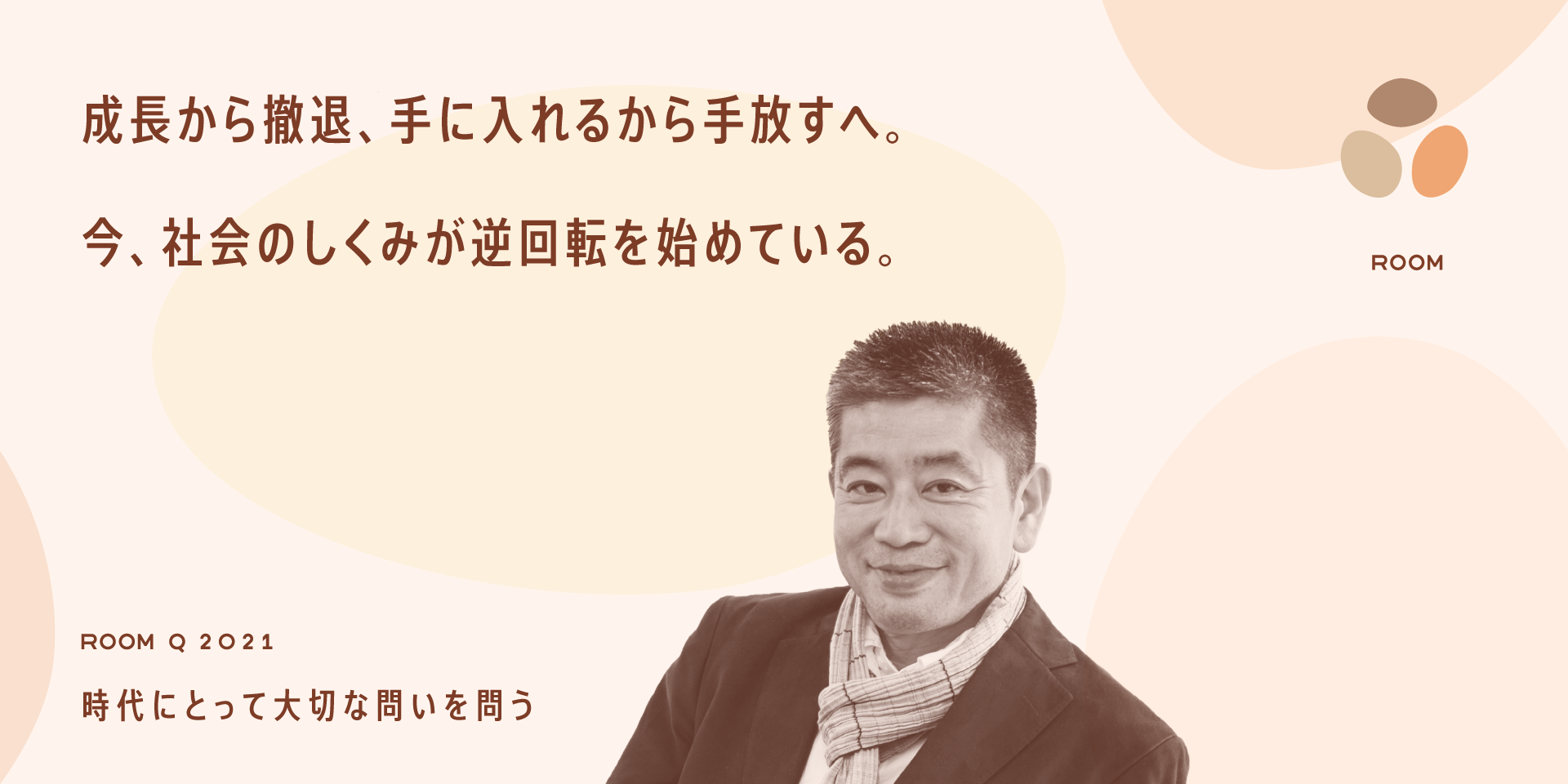社会の進化を促す「アウェアネス」とソーシャル・イノベーション【ミラツクフォーラム2017】
毎年末、ミラツクにゆかりのある多様な領域の方々をお招きし、一年の振り返りと総括を行う「ミラツク年次フォーラム」。2017年12月23日、東京・日本橋の「株式会社デンソー東京支社」にて開催されました。当日は全国から集まった約100名の参加者が会場を埋めるなか、各分野をリードする豪華ゲストによる計10本のセッションが行われ、1年を締めくくるにふさわしいイベントとなりました。
オープニングを飾ったのは、慶應義塾大学特別招聘准教授の井上英之さん、京都市ソーシャル・イノベーション研究所所長の大室悦賀さんによる基調対談。ミラツク代表・西村の進行で「すでにある未来とソーシャル・イノベーション」をテーマに白熱したトークが展開されました。幅広い知見とユニークな発想が飛び交う対談の様子をお伝えします。
 この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
登壇者プロフィール
慶應義塾大学 特別招聘准教授、NPO法人ミラツク アドバイザー
2001年から、NPO法人「ETIC.」にて、日本初のソーシャルベンチャー向けプランコンテスト「STYLE」を開催するなど、若い社会起業家の育成・輩出に取り組む。2003年、NPOや社会起業にビジネスパーソンのお金と専門性を生かした時間の投資をする、「ソーシャルベンチャー・パートナーズ(SVP)東京」を設立。2005年より、慶応大学SFCにて「社会起業論」などの、ソーシャル・イノベーション系授業群を開発。「マイプロジェクト」と呼ばれるプロジェクト型の手法は、高校から社会人まで広がっている。2012~14年、米国スタンフォード大学、クレアモント大学院大学に客員研究員として滞在した。近年は、マインドフルネスとソーシャル・イノベーションを組み合わせたリーダーシップ開発に取り組む。軽井沢在住。
京都市ソーシャル・イノベーション研究所 所長、NPO法人ミラツク アドバイザー
1961年、東京都生まれ。「株式会社サンフードジャパン」、東京都府中市庁への勤務を経て、2015年4月より、京都産業大学経営学部教授に就任。著書に、『サステイナブル・カンパニー入門』『ソーシャル・イノベーション』『ソーシャル・ビジネス:地域の課題をビジネスで解決する』『ケースに学ぶソーシャル・マネジメント』『ソーシャル・ エンタープライズ』『NPOと事業』などがある。社会的課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・ビジネスをベースに、NPOなどのサードセクター、企業セクター、行政セクターの3つのセクターを研究対象として、全国各地を飛び回り、アドバイスや講演を行っている。
社会の課題を解決し、より良い未来をつくるのは誰か?
西村「ミラツク年次フォーラム」はここ数年、井上さんと大室さんの基調対談でスタートするのが恒例となっています。同じ顔ぶれで、一年を通じて得た気づきや感じたことをライブで探求しながら、ソーシャル・イノベーションにまつわる既成概念を毎年アップデートしていくのが目的です。今回は「すでにある未来とソーシャル・イノベーション」をテーマにお話を進めていきます。まずは簡単な自己紹介からはじめましょうか。
井上さん皆さんおはようございます。井上と申します。「ミラツク年次フォーラム」には初回から登壇させていただいていますが、毎年参加者の顔ぶれに変化を感じています。ソーシャル領域の方々が大半だった開催当初に比べ、近年は企業関係の方々が増えている印象があります。私感ですが、企業の現状に強い危機感を持ち、具体的に変革を起こすためのヒントを求める熱意ある企業人が増えている気がしますね。
西村会場に聞いて見ましょうか。企業に所属している方、どのぐらいいらっしゃいますか? かなり多いですね。
井上さんなぜ自己紹介の前にこんな話をしたかというと、会社で働く企業人の姿こそが僕の原体験だからなんです。
僕は埼玉県越谷市出身ですが、両親の意向で小学生の頃から東京の進学塾に通っていました。塾に向かう満員電車では、大人たちがみんなイライラしていました。車内でよろけると、子どもでも容赦なく小突き返されたり、舌打ちされたりするわけです。大人は皆、偉人伝のようにかっこよくなると信じていた当時の僕にとって、彼らの振る舞いはとても衝撃的でした。
人々が仕事を通じて自らを発揮し、よりよく生きられる社会をつくる活動をはじめたのは、そういう原体験があったからです。まだ日本で社会起業やソーシャル・イノベーションが認知されていなかった2000年代初頭、僕はいち早く社会起業に特化したビジネスプランコンテストを立ち上げ、ソーシャルベンチャーを支援する投資団体「ソーシャルベンチャー・パートナーズ(SVP)東京」を設立しました。また「慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス」で社会起業をテーマにした授業群を開発し、NHKでソーシャル・ビジネスに関する番組を制作したり、政府の委員会にかかわったりもしました。
一連の活動の背景にある僕の願いは、ずっと変わりません。世界トップクラスの経済力を誇る日本のビジネスパーソンが、それぞれの専門知識やスキルを、より良い社会づくりのために提供できるしくみをつくりたい。そうすれば、この世界をもっと大きく変えることができる。そんな思いで、走り続けてきました。
井上さん近年はソーシャル領域にも多くのプレイヤーが参入するようになりましたが、その一方でバーンアウトする人も目立ってきています。なぜなら、社会課題の解決には中長期で長い時間がかかる上、継続的なリソースが集まりにくく、すぐには目に見える結果に結びつかないからです。
彼らがどんなに頑張っても、そんな早急には、目に見えるインパクトにはつながらない。そして、気づくと自分の体調や本当に大切にしたいものを無視して、無理強いにでも世界を変えようとしてしまう。本当は、誰のなかにも変化を生み出す力があって、それを手伝うのが大切なはずなのに。それならば、自分自身につながり、自分のセルフマネジメントができていることが、結果としては、変化を生み出す近道にもなるんじゃないか?――そう思うに至りました。
そこで僕は、日本財団の国際フェローシップで米国カリフォルニアに渡り、2012年から2年間、瞑想に代表されるマインドフルネスやセルフマネジメント、そしてそれらの科学的根拠となる脳科学や心理学を学びました。今はこれらの知見を生かし、若いソーシャルリーダーの育成や、企業内のソーシャル・イノベーション支援、研修プログラムの開発などに従事しています。よろしくお願いします。
西村井上さん、ありがとうございました。続いて大室さん、お願いします。
大室さん大室と申します。肩書き上は「京都市ソーシャル・イノベーション研究所」所長ということになっていますが、本業は「京都産業大学」の教員です。井上さんと初めてお会いしたのは、たしか1990年代の前半でしたよね? 当時、僕はNPOをはじめとするソーシャル分野に大きな可能性を感じていて、そんな流れのなかで井上さんと知り合った記憶があります。
今はソーシャル・ビジネスの具体的な支援からは少し距離をとって、企業研究に専念しています。企業研究をはじめた理由は、世界が抱える社会課題はすでに行政やNPOの力だけでは解決できないところにきていると感じたからです。社会課題の多くは、実は市場、つまり企業によって生み出されています。市場の外側から働きかけても問題を解決できないなら、内側から解決するしかない。つまり、企業の努力によって社会課題をそもそもつくらないアプローチが必要だと考えたのです。
例えば、子どもの貧困問題。行政やNPOにできることは「こども食堂をつくる」といった対応に限られるでしょう。しかし、これはあくまでも対症療法なんです。根本的な解決には、政治的に所得の再配分を促したり、企業が非正規雇用の賃金を底上げするなど、問題を生んでいる社会背景から変えていく根治療法が必要です。そのためには市場や政治のシステムの変革が避けられません。そこで企業が果たす役割は非常に大きいでしょう。
そしてもう一つ、社会の変革に欠かせないのが市民力です。市民力とは、要するに我々一人一人が社会課題の解決を自分ごとと捉え、社会の一員としてのマインドを育んでいくことです。一人一人の力を高め、どれだけパフォーマンスを上げていけるか。来年以降は、企業研究だけでなく、そんな個の力を高める活動にも注力していきたいと思っています。
また来春には、長野市の長野県立大学に「ソーシャルイノベーション創出センター」が開設されます。私はセンター長として、全国からさまざまなプロフェッショナルを招聘し、産学官が連携しながら地域課題の解決を目指していく予定です。よろしくお願いします。
前提を揺さぶる「アウェアネス」が社会進化を加速する
西村大室さん、ありがとうございました。本題に入る前に、僕がこの一年で個人的に興味を持ったことを共有したいと思います。
一つ目は、社会課題の解決という行為を、どうしたら自分たちのミッションという文脈に取り込んでいけるか。「ミッション=社会課題の解決」という構図だと、なかなか自分ごとにならないし、興味も持てない。でも「ミッション=自分たちが願う社会、欲しい未来をつくる」であれば、もっと工夫したり、楽しみながら取り組めるかもしれない。理想の未来を目指していたら、結果的に社会課題も解決した、ということもあり得るんじゃないか。要は、社会課題の解決そのものをミッションにする必要はない、この感覚をうまく言語化したいな、と。
二つ目は、去年の基調対談でも話題に出た社会進化について、お二人と掘り下げた議論をしたいと思っています。僕はこの一年、社会の進化について徹底的にリサーチしていたんですが、その過程で最も印象に残ったのが「ギョベクリ・テペ」という古代遺跡にまつわる仮説なんですね。
「ギョベクリ・テペ」はトルコ南東部で発見された人類最古の宗教遺跡で、およそ1万4000年前に建設された神殿といわれています。興味深いのは、「ギョベクリ・テペ」がつくられたときはまだ農耕が始まっていなかった、ということ。つまり人々は、狩猟中心の移動生活にもかかわらず、互いに協働しながら長い時間をかけてこの巨大な遺跡をつくったんです。
実際、遺跡周辺には農耕や定住の痕跡がないんですよ。つまり、都市が先に形成され、後から農耕が誕生したことを強く示唆している。その結果、これまで「農耕の始まりによって都市が誕生した」とされていた考古学の常識を覆してしまったんです。
都市は農耕文化の結果ではなく、「みんなでここに集まって一緒に何かをしたい」という人々のコミュニティ意識によって生まれたのかもしれない。そう気づいたら、人々がなぜ進化の過程で狩猟生活を捨て、手間と時間のかかる非効率な農耕を選んだのか、という長年の謎が解けたんです。要は、因果関係が逆だったんですね。
人々は手探り状態のなか、そこから何千年もかけて農耕のノウハウを確立しました。それは言い換えれば、やり方を知らなくても試行錯誤のなかでちゃんと社会は進化する、ということじゃないでしょうか。同じくやり方がわからないまま社会課題の解決に取り組む僕らにとって、すごく希望の持てる話ですよね。社会の進化は、ある課題が解決されなければ先に進めない、というものではなく、さまざまな問題や矛盾を孕んだまま前に進んでいくものかもしれない、と。もしそうであるならば、僕らが課題解決に取り組む姿勢や手法にも、もっと別のアプローチがあるかもしれない。逆説的ですが、そういう視点からソーシャル・イノベーションの意義を捉え直してみたいな、と。
大室さん社会の進歩や進化を考えるなら、分子生物学者の福岡伸一さんが提唱する「動的平衡」という考え方が参考になるかもしれません。我々の体内では常に新陳代謝が行われていて、古くなった細胞は破壊され、新しい細胞に取って代わられます。言い換えれば、古くなった細胞が破壊されて体外に排出される前に、それに取って代わるだけの新しい細胞があらかじめ生成されているということです。「動的平衡」とは、絶え間なく繰り返される破壊と生成の流れのなかで、体全体としての恒常性が保たれている状態、といえます。
我々の社会も同じで、何かが失われたり壊れたりするのを、先行してクリエイトされた何かが補うことで社会全体としての恒常性が維持されている。でも、この代謝機能が落ちてくると、社会はどんどん病気がちになり、停滞していく。つまり代謝システムを刷新し、人々が先行して何かを生み出す力を取り戻さないと、社会の進化はどんどん鈍化していくわけです。
今こうしている間にも、人々は常に「先行して何かを生み出す」行為をしているわけですが、現代社会ではそれらが企業というフレームのなかで行われることも多い。市場が人々の生活に大きなインパクトを与える現代では、この代謝システムにおいて、企業の活動の存在感はどんどん高まっている。そういう意味では、企業は人類が進化するための道具といえるかもしれない。
一方、本来、人類が進化するにはコミュニティが必要でした。なぜなら、人間は一人だとなかなか進化しないんですね。あの仏陀でさえ、一人ではなかなか悟りを開けなかったぐらいですから。先ほどの勇哉くんの仮説のように、やはり人間の進化にはまずコミュニティありきで、そのなかで成長していくことが効率的なんです。
これまでは地域コミュニティやNPOなどがその役目を担っていたと思うんですけど、市場が社会に対して支配的になるにつれ、企業がそこに取って代わってしまった。今はそういう状況じゃないかな、と思っています。でも、企業は営利を目的に活動しますから、いわゆるコミュニティとしての機能は本来持っていないし、地域や社会への貢献も第一義ではない。近年は企業の姿勢もだいぶ変わってきましたが、まだまだ十分とはいえないでしょう。
このように人類の進化を支えてきたコミュニティ機能が事実上、失われてしまっている今、重要なことは、我々一人一人がそれぞれ自らを成長させていくことにほかなりません。もちろん成長といっても、何か崇高な目標を立てるとかそういうことではなくて、「何のために生きているのか」「自分はどこへ向かうのか」と自分に問う、その問いかけだけで十分だと僕は思っています。
仏教的な話になりますが、とにかく「今、ここに在ること」を意識し、今を楽しみ生きることに集中する。そんなある種のマインドフル状態を保つことが、結果として人類の進化や社会の進化に貢献していくのではないか、と。社会の進化を考えるなら、西洋的な哲学だけでなく、こういう東洋的な哲学も加味して再考しないといけないな、と改めて感じた次第です。井上さんはどうですか?
井上さん西洋社会では、よく農業革命という言葉がキーワードとして出てきますよね。農業革命によって定住が可能になった、それが人類にとって大きな進化のきっかけになった、そういう認識なんですよね。
一方で、こういう見方もあります。いったん農業をはじめてしまってから、人間は休めなくなった。僕も軽井沢に住んで野菜を育てているからわかりますが、野菜には土日とか祝日なんて関係ないんです。だから僕たちは休めない。
世界的ベストセラーの『サピエンス全史』は、その状況を「小麦の奴隷」と表現しています。生きるためにはじめたことが、いつのまにか逆転して農業生産するために生きている、と。さらに、農業は人類に多大な恩恵を与えた一方で、所有の概念や貧富の格差、グループ内の上下関係など現代の都市問題の背景となるパラダイムを生み出した、とも指摘している。
で、勇哉くんに確認なんですが、この西洋社会では前提とされている「農耕の発明→都市の誕生→都市問題」という言説を、「ギョベクリ・テペ」が覆してしまったことについてコメントすればいいのかな?
西村前提を覆したことより、その前提が前提になり得たことが疑問だったんですね。手っ取り早く高タンパク高カロリーが得られる狩猟生活を捨てて、手間もかかる上に低カロリーしか得られない農耕生活を選ぶなんて、進化として矛盾しているじゃないですか。だから「ギョベクリ・テペ」の存在が示す仮説が衝撃だったんです。
人類は脳が発達する過程で死の恐怖や自己を認識するようになり、やがて想像力を手に入れました。そして宗教や信仰が生まれ、人々は神殿をつくるに至った。そこで「ずっと神殿の近くにとどまっていたい」という「欲しい未来像=定住志向」が生まれたわけです。その欲しい未来を実現しようとした結果、移動せずに食料を得る手法=農耕が生まれた。よく考えればすごく自然な流れなのに、どうして今まで気づかなかったんだろう、と。
井上さん なるほど。僕が思うに、我々が前提として当然のように信じていること――例えばビジネスのやり方であったり、朝起きて学校に行くことだったりすること――それらを僕たち自身がどれだけ意識できているか。それが進化にもすごく重要だと思うんです。
米国の著名な経営学者であるPeter M. Senge(ピーター・センゲ、以下センゲ氏)は、進化論や進化生物学にもよく言及していて、彼はあるスピーチのなかで「あらゆる生物はニッチ(生態的地位、ある生物種が生息する特別な環境)でしか生きられない」と語っているんです。
ペンギンが飛べなかったり、キリンの首が長かったりするのには全て理由があって、彼らがそれぞれのニッチに(ほかのどの種よりも高く)適応することで生き延びてきたからにほかならない。もちろん人類も例外ではなく、熱帯のジャングルから乾燥した砂漠まで、さまざまなニッチに自らの肉体や食事、言葉、文化を適応させながら進化してきました。だからこそ、じつに多様な人種や民族、言語が生まれた。すでに滅んでしまったものも多いけれど、今も世界中のあちこちに、数千年前と変わらぬ暮らしをしている人々は存在しています。
センゲ氏のスピーチに、約1万5000年前から同じ場所で同じ暮らしを続けているブラックフット族という先住民族の話が出てきます。興味深いのは、彼らの言語には名詞がないらしいんですよ。「これは〇〇だ」のように物事を定義せず、すべてを状態やプロセスで言い表しながら世界を把握している。センゲ氏はそれを「ニッチに適合するための進化である」というわけです。
名詞のない世界なんて僕には想像もつきませんが、よく考えれば日本にも似たような事例はあるんですよね。例えば文明開化以前、日本語には「自然」という単語がありませんでした。自然があまりにも身近すぎて、その存在を意識できていなかったんですね。自分は自然の一部だから、わざわざ言葉を与えて区別する必要もなかった。ところが、文明開化という環境変化によって「nature」という外来語が入ってきた。そこで当時の日本人は「自然」という言葉をつくって適応したんです。
つまり、今我々が手にしているあらゆるモノや生活様式、文化、言葉、価値観は、日本人が長い時間をかけてニッチに適合してきた結果、存在しているものなんですよね。当たり前すぎて意識すらしなかったこと、疑いすら抱かなかったことに耳を済まし、気づき意識化すること――そんな「アウェアネス」が、社会の進化には非常に大事なんだと思います。
固定化したフレームを解放し、未来に目線を向ける
大室さん井上さんがここに持ってきてくれている『能』という本の著者で、能楽師の安田登さんと京都でお会いしたとき、「能は何のために存在するのか?」という話をしたんです。
先ほどの話にも関連しますが、西洋世界では「キリストがいて民がいる」という構造なんですね。一方、日本の伝統的な世界観は、おそらく能の舞台を観るとよくわかると思うんですが、あらゆるモノが仏や神の化身として我々の周囲に偏在しているイメージなんです。
それらはいわば自己を投影し、客体化してくれる鏡のような存在。つまり我々は、能を鑑賞しながら自分を見つめ直している。だから能は、最小限の動きでも非常に豊かなものを感じさせてくれる。
脳科学的にいうと、人間はさまざまな感覚や知覚、感情、他者とのかかわりなどの状態やプロセスを統合することで自己を認識しています。要するに人間は他者、つまりコミュニティがないと、自分を認識することすらできないんです。
今日この会場でも、さまざまな人たちが集まって、自分とは異なる他者との対話をしながら、彼らの姿を立体の鏡のようにして自分を投影しているんですね。いろいろな人との対話によって自分を客体化すると、井上さんがいう「アウェアネス」のように、自分のなかで勝手に前提にしていた考えや問題点に気づいたり、再考することができる。だから脳科学的に見ても、コミュニティ化するのは進化のために最適な戦略なのです。
西村未来とソーシャル・イノベーション、そして社会進化は、ダイレクトにつながっている気がします。そういう風に少し未来に目線を持っていく、つまり「アウェアネス」を得るためには、何か有効な方法はあるんでしょうか。
井上さんでは、ちょっと実践してみましょうか。(会場に向かって)皆さん、リラックスできる姿勢で30秒ぐらい呼吸を整えてみてください。肩に力を入れず、瞑想するような気持ちで。それから、この部屋を、初めて見るように、改めてよく観察してみてください。
天井の色やカーテンの形状、窓の外や空間の奥行きなど…… 改めて観察しなおすと、さまざまな発見があったと思います。これを「リニューアル・アテンション」と呼びます。いつもの職場や通い慣れた通勤の車内などでやってみるとわかりますが、同じものが違うように見えたり、おもしろい発見があったりします。要は、今まで世界を見ていたときのフィルターをリセットしてみる。過去のパターンの連続ではなく、今、ここに注意を払って、改めて見る、それまで見えていなかったものが見えてきて、新たなリソースも浮かび上がってくる。我々の内側にある注意の向け方を変えると、外部の世界も変わるんです。これが「アウェアネス」の非常に大事なポイントです。
大室さん「アウェアネス」でいうと、僕もこの一年、多数のエンジニアの方々と関わる機会を通じて気づいたことがあります。「なぜエンジニアはデザイン・シンキングに囚われるのか」と。彼らは何事も技術ありきで考えるというか、新しい技術しか見えなくなってしまう。技術によって蛸壺化してしまうんですね。
「どうしたら彼らを説得できるか?」と模索するうちに出会ったのが、アート・シンキングという考え方です。デザイン・シンキングが問題を解決するための思考なら、アート・シンキングは既成概念に問いを投げかけ、批評的な視点から新たな価値を見出す思考を意味します。井上さんのいう「アウェアネス」とほぼ同義といえるでしょう。
例えば、100人に井上さんの絵を描かせたとします。完成した絵は、写真のようにリアルなものから、もはや人間に見えないような抽象的なものまで、さまざまだと思います。なぜなら、描き手が見ている井上さんは同じでも、描き手が捉える“井上さんのイメージ”はそれぞれ違うからです。自分は絵を通じて何を社会に問いたいのか。観る人に何を感じてほしいのか。そういった哲学的な命題を含む思考をアート・シンキングというんです。
一方、企業のプロダクトをつくっている人たちは、問題解決が念頭にあるので、絵が非常に陳腐なんですね。未来像も陳腐なものしか描けない。だから技術とも全然つながらない。ところがアート・シンキングを取り入れて作業していくと、すごくおもしろいものができたりする。
人間は誰しも、これまで生きてきたなかで獲得した「こうあるべき」というフレームを、無意識に実装してしまっているんですね。そのままだとイノベーションにもつながらないし、未来も描けない。今、日本のものづくりがぶつかっている壁はそこなんです。だからアート・シンキングを活用しながら、固定化したフレームを解放してあげる作業が必要。それは多分、勇哉くんのいう「目線を未来に向ける」ことにつながる。つまり、未来の設定の仕方でイノベーションは変わるんです。
井上さん最近周囲の人たちとの間で「ソーシャル・イノベーション分野から本当にソーシャル・イノベーションは生まれるのか」というテーマが話題に上るんです。今の大室さんの指摘に近いですが、課題を解決しようとばかりすると「これが課題である」というフレームの固定化が起きて、かえって新しい発想が生まれない、ということが起きる。つまり「これが課題である」というマインドを手放さないと、課題の本質や背景に気づけなくなってしまうんですね。だからこそ「自分は今、どんな前提で何を見ているのか」を自覚し、「アテンション」(注意)の向け方を変えてみることが大事なんです。
というのも、人間の「アテンション」の絶対量は限られているんです。心理学者のMihaly Csikszentmihalyi(ミハイ・チクセントミハイ)がある論文に書いていましたけど、人間の「アテンション」にはキャパシティがあり、どこかに向けるたびにその残量はどんどん減っていくんです。つまり人間は、あまりマルチタスキングに向いていない、と。言い換えれば、何かに「アテンション」を向けることは、ものすごく貴重な行為なんです。
その貴重な「アテンション」を自分は今どこに向けているのか意識し、意図して向け方を変えると、新しい「アウェアネス」が得られる。これまでと同じ状況や場所でも、気づいていなかったリソースに気づく。新たなリソースやその組み合わせに気づくと、創造的に目の前の「チョイス」(選択肢)が増える。「チョイス」が増えれば、これまでになかった「アクション」(行動)を選択し、当然「リザルト」(結果)も変わる。アテンションを変えることで、新しいリソースに気づき、新しい行動の選択肢が生まれるんですよね。まさに創造性の源泉だと思うんです。
このとき、自分の行動の「リザルト」(結果)を見て、では、これは本当に自分が欲しい結果なのか?という自分の「インテンション」(意図)に気づくことができる。私たちの瞬間瞬間の意思決定の95%以上は、無意識で行われているといいます。その無意識的な意思決定の多くは、これまでのパターン的な行動に基づいていて、僕たちは、別に健康を壊したいという意図はもっていないけど、なぜだか自動的に夜中にチョコレートを食べたりします。それで太ってしまって、あれ、これでよかったんだっけ?と。今の行動の結果は、本当には欲しい未来でないのであれば、では、自分は何を求めているのか?より明確な「インテンション」に基づいて、改めて、自分の食事や生活に目を向けてみる、「アテンション」を変えてみる。それがまた、新しい「アウェアネス」(気づき)につながる……。
このサイクルの繰り返しで、自分に気づいていくことを通じて、より画素数の高い「インテンション」やビジョンをもてる、つまり先ほど勇哉くんがいった「目線を未来に向ける」こともできるようになる。例えば、大学生たちに「将来どんな仕事をしたいか」「どんな未来が欲しいか」と尋ねても、たいてい答えられないですよね。なぜなら、彼らの多くは何かをやってみた、行動してみた「結果」を充分に持っていないので、情報が足りないんですよ。
実際に行動して得られた結果というのは、ものすごい価値のある情報源です。結果って、データなんです。だからこそ、どんな些細なことでもいい。家庭や職場、よく行くコンビニでのやり取りでもいい。何かをやってみること。そこから情報を得ることなんです。「アテンション」の向け方は、目線を未来に向けるための、大事なはじめの一歩なんです。
西村なるほど。目線を未来に向ける方法がわかった気がします。それでは最後に、お二人のコメントでセッションを締めたいと思います。
大室さん今日は皆さんに「複雑なものを複雑なままに捉える」という視点を、ぜひお持ち帰りいただきたいですね。世の中のほとんどの人は、知らず知らずのうちに自分の過去の失敗、あるいは成功体験を分析して、今の行動を決めていると思います。でもそれって、未来に背を向けて、過去に起こったことを検証しているだけなんです。
今いる環境に慣れすぎてわずかな変化に気づけず、危機的な状況に追い込まれることを「ゆでガエル症候群」と呼びますが、これも過去に囚われるがゆえの失敗例の典型です。
だから過去の分析ではなく、複雑なものを複雑なものに捉える工夫だけをしましょう。それは「アテンション」の向け方を変化させ、やがてイノベーションにつながっていくのですから。
井上さん僕は今日のメインテーマである進化の話で締めたいと思います。進化生物学の見地からいうと、生物はこれまで非常に合理的かつ戦略的に進化してきました。ただ、人間の場合、人類の進化や社会の進化という視点からいっても、単なる周辺環境やニッチへの適合だけではなく、人間独自の要素もあるんじゃないかと僕は思うんです。
例えば、米国クレアモント大学ピーター・ドラッカースクール准教授で、僕のマインドフルネスの師匠でもあるJeremy Hunter(ジェレミー・ハンター、以下ジェレミー)は、20代の頃、腎臓の病気で余命宣告されたんですね。彼はその後、腎移植を受けたため今も健在ですが、当時は「数年以内に90%の確率で亡くなる」といわれていたそうです。
興味深いのは、ジェレミーが余命宣告されたにもかかわらず、「自分はラッキーだ」と考えた点です。聞けば、彼は「生き残れる確率が10%もある!」と解釈したというんです。
もしこれがAIだったら、この状況を絶対に「ラッキー」とは判断しないでしょう。「数年以内に90%の確率で死ぬ」という条件に対する合理的な理解は、おそらく「助からない」です。しかし人間は「生存確率が10%もある」と信じることもできる。どんなに非合理でクレージーな主張でも、主観として選択できるんです。つまり「インテンション」ですね。我々は意志の力や夢や希望によって、欲しい未来を思い描き、行動することができる。それは人間だけが生み出し得る未来のかたちの一つであり、適合するだけではない、私たちの進化に関する重要な部分でしょう。
だからこそ「未来をつくる」で「ミラツク」なんです!
(会場拍手)
大室さん進化を意識することは必要なんですが、それ以上に大切なことは、今ここを楽しむ、ということ。今日の学びは、後になってきっと生きてくると思います。だから今日は午後のセッションも存分に楽しんでください。僕からは以上です。ありがとうございました。
西村お二人には毎回変なテーマを投げまくっているのですが、本日もちゃんと受け取っていただけて大変ありがたかったです。井上さん、大室さん、本日はありがとうございました。
 この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/
ROOMの登録:http://room.emerging-future.org/
ROOMの背景:https://note.com/miratuku/n/nd430ea674a7f