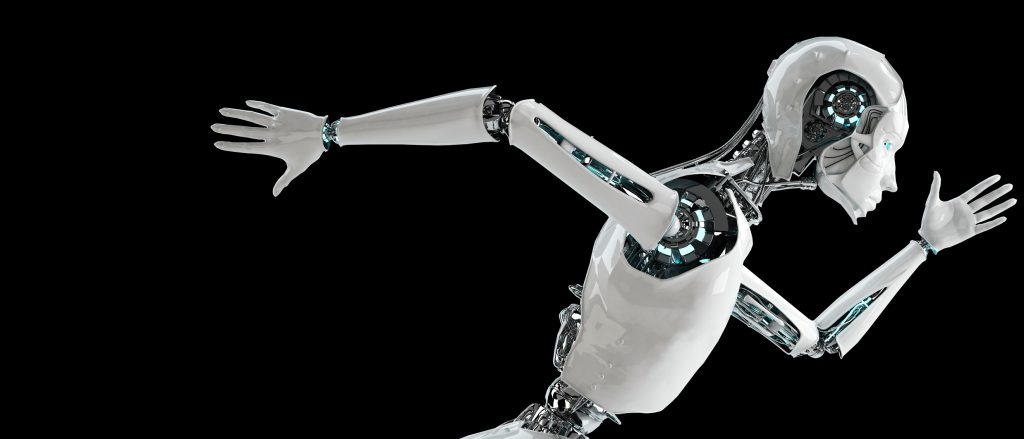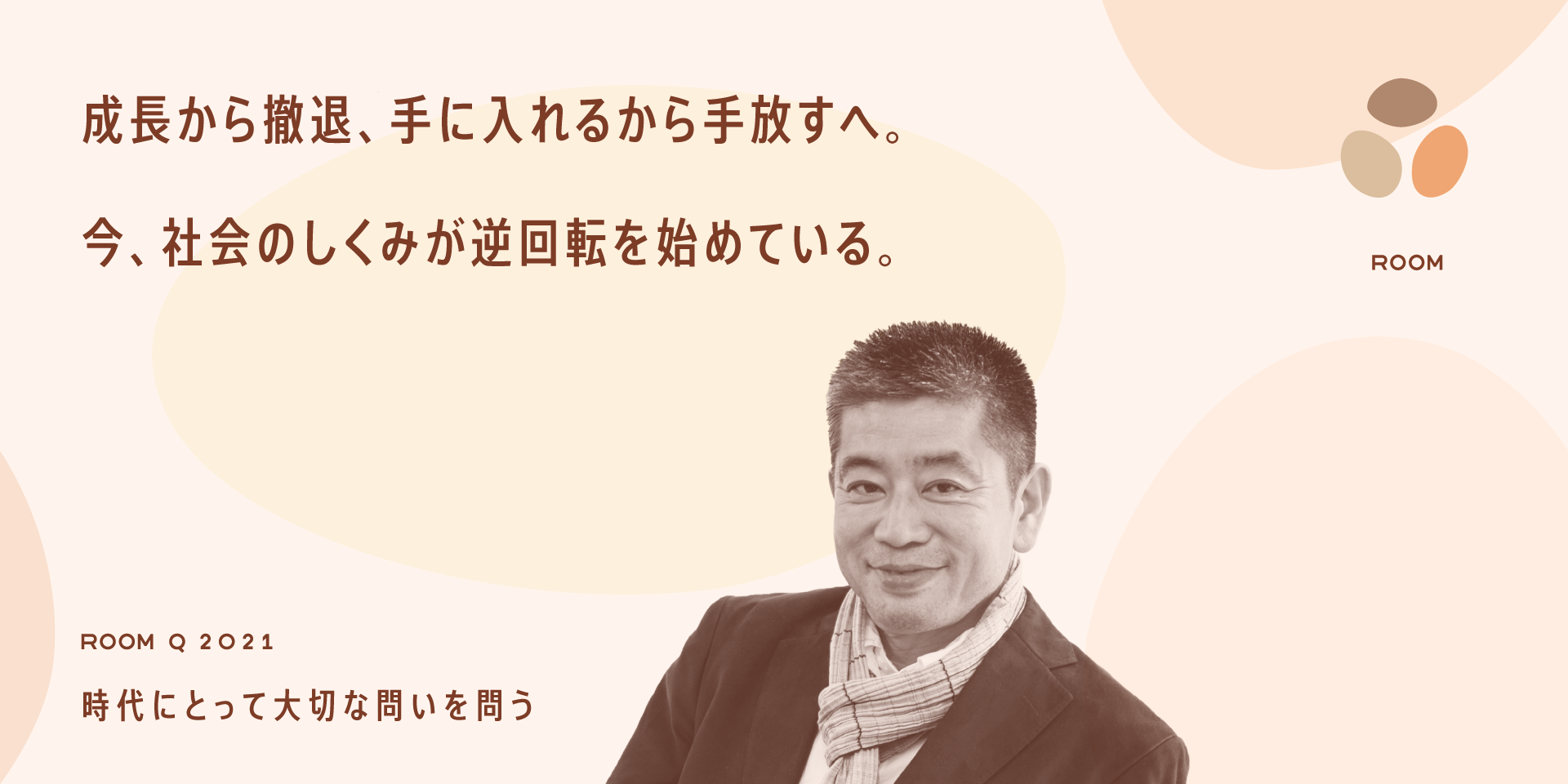瞬間移動技術によって、あらゆる人が身体的制約から解き放たれる未来を。avatarin株式会社代表取締役CEO・深堀昂さん【インタビューシリーズ「未来をテクノロジーから考える」】
シリーズ「未来をテクノロジーから考える」は、ミラツク代表・西村勇哉がインタビュアーとなり、「テクノロジーを駆使して未来を切り拓く」活動を行なっている人たちにお話を聞くミラツクのメンバーシップ「ROOM」がお届けするオリジナルコンテンツです。12/23に開催されるミラツク年次フォーラムではROOMと連動し、インタビュイーをお招きしたセッションを開催しています。
開催日時:2020年12月23日(水) 9:30-20:00 at オンライン
◯セッション3-A「未来への投資をデザインする」(15:15-16:30)
米良 はるかさん READYFOR株式会社 代表取締役 / CEO
白石 智哉さん ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 理事
深堀 昂さん アバターイン株式会社 代表取締役CEO
田崎 佑樹さん KANDO 代表、アーティスト
モデレーター:NPO法人ミラツク 代表理事 西村
◯詳細・参加登録:http://emerging-future.org/news/2400/
「アバターによって瞬間移動体験が可能になり、誰もが社会課題解決に参画できる世界中とつながるネットワークを構築できる」と語る深掘さん。アバターインが行なっている取り組みはなぜ画期的なのか。従来のロボット技術開発や研究が抱えていた課題とは。「人間=身体」なのか、人間とは何か、という根源的な問いに向き合い続けている深堀さんが見る未来について伺いました。
(構成・執筆 代麻理子)
avatarin株式会社 代表取締役CEO。
2008年、ANAに入社。パイロットの緊急時の操作手順などを設計する運航技術業務のかたわら、営利と非営利のタイアップモデル「BLUE WINGプログラム」を発案する。Global Agenda Seminar 2010 Grand Prize受賞、2011年世界経済フォーラムに参加、南カルフォルニア大学MBAのケーススタディーに選定。2014年より、ANAのプロモーションを担当し、ウェアラブルカメラで撮影したビジネスクラス体験プロモーション「YOUR ANA」を企画、実行。2016年には、クラウドファンディングサービス「WonderFLY」を発案。XPRIZE財団主催の次期国際賞金レース設計コンテストにて、「ANA AVATAR XPRIZE」のコンセプトをデザインしグランプリ受賞、2018年3月に開始し、現在82カ国、820チームをこえるグローバルムーブメントを牽引中。2018年9月、JAXAと共にアバターを活用した宇宙開発推進プログラム「AVATAR X」をリリース、2020年4月、アバターイン社を立ち上げる。
「人間=身体」なのかという根源的な問い
西村まずはじめに、深堀さんがアバターインでどんなことを行なっているのか、から始めたいと思います。
深堀最先端技術を駆使したアバター(遠隔操作ロボット)によって、物理的距離と身体的限界をゼロにする瞬間移動体験を、社会インフラ化しようと試みています。僕はもともと「75 億人の人に夢と感動を届けたい」という思いが強く、大学では航空宇宙工学を専攻し、卒業後はANAに入社しました。
アバターインを設立するまでの12年間、ANAに所属しながら「世界中の人に夢と感動を届けるにはどうしたらいいのか」を模索していたのですが、社会実装を考えたらANAから独立してスタートアップとして邁進したほうがより早くそれを実現できるという結論に至り、2020年4月にアバターインを設立しました。
アバターインが具体的にどのようなことを行なっているのかというと、独自に開発した技術によって「身体的にはその場にいなくても、その人がそこに存在する」という状況をつくり出しています。そのことを「瞬間移動を可能にする」と表現しているのですが、弊社が提供している「newme(ニューミー)」というコミュニケーション型アバターロボットは、ロボットだけどロボットではないと僕は思っていて。つまり、限りなく「私」なんですね。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「NEDOロボット白書2014」(2014年3月)では、ロボットとは「センサー、知能・制御系、駆動系の3つの要素技術を有する、知能化した機械システム」と定義されています。ですが、ニューミーは知能化した機械システムというよりも、ユーザーそのものなんです。その人の存在感まで伝送できる。
生物を用いての実験から、そのことがよくわかります。写真を見ると「何を言っているんだ、ただのタブレットがついた機械じゃないか」と思われるかもしれませんが、ニューミーを水族館のマナティの水槽の前に置いて人がアバターに入り、過ごしていると、次第にマナティが懐いてくるんですね。同じことをZoomなどのオンライン会議ツールで行なってもマナティはまったく反応を示しません。
僕は「人を人たらしめる要素はなんなのか」という問いを抱き続けてきました。その問いを突き詰めていくと、「人間=身体なのか」という問いと向き合うことになります。その結果、身体はもちろん要素としてはありますが、それがすべてではなく「意識=人間」なのではないかと思うに至りました。そして意識は、インターネットを介すとコンピュータに指示を出すことによって光の速度で送信できます。
そう考えると「移動=身体を動かす」という概念はもう終わりで、これからは意識だけを瞬間移動するのもモビリティの枠組みに入ってくるのではないかと、僕は考えています。
小学生の頃から向き合っていたソーシャルムーブメントの起こし方
西村そこに至るまでの経緯なども順番に伺えたらと思うのですが、そもそもなぜ深堀さんはアバターインを興そうと思ったのでしょうか?
深堀少し遡ってお話すると、僕の父は転勤族だったこともあり、幼い頃から飛行機に乗る機会が多かったんですね。さらに、米国に住んでいた4歳から11歳までの6年間はNASAで行われるワークショップにも参加したりと、航空・宇宙系への興味が強い子どもでした。加えて、当時米国で通っていたモンテッソーリスクールの影響からか、小学生の頃からソーシャルインパクトを出すことをかなり重視していて。NASAジェット推進研究所(JPL)に手紙を送ったり、資料を取り寄せたりしていました。
帰国後は群馬の公立小学校に転入したのですが、給食の牛乳パックが捨てられていたことに疑問を感じ、洗ってトイレットペーパーに再製するというムーブメントを興しました。それが群馬県と栃木県のルールになるなど、とにかく社会的にインパクトを出すにはどうしたらいいのか、ということは小さい頃から考え続けてきました。特に群馬では、社会課題に興味がない人に対して、どうリーダーシップを発揮し、同じ方向を向いてもらうかについて多くを学びました。
大学在学中にはNGOやNPO、国連職員などの取り組みを持続的に発信するためにWebサイトを立ち上げたり、廃棄割り箸を木のおもちゃに加工して保育園に届けたりといった活動を行なっていました。ANAに入社後はそうした活動を並行して行いながら、一橋大学名誉教授である石倉洋子さんが主催するグローバル・ゼミに参加しました。2010年頃のことです。そこでグローバルに通用するビジネスモデルの考え方を学び、プロジェクトとして形にしたのが「Blue Wing」です。西村さんとも「Blue Wing」を通じて出会いました。
その後、クラウドファンディングのプラットフォーム「Wonder FLY」を立ち上げたりと、大企業の中でのイノベーションの起こし方については試行錯誤を繰り返してきました。そうした経緯を経て立ち上げたのが、アバターインです。僕はそれまで業務外で何かを考えて、お墨付きをもらってから社内に持ち込んで実行するというのが、ANAでの進め方だったんですね。
西村「深堀流」ですね。
深堀そうかもしれません(笑)。アバターインに関しては、2016年の10月に米XPRIZE財団主催のコンペティションでのグランプリを受賞したことをきっかけに、高性能アバターを開発する賞金総額10億円の国際賞金レース「ANA AVATAR XPRIZE」がスタートしました。2018年には正式に「アバタープロジェクト」を立ち上げ、さまざまなアバターの実証実験を産官学で進めながら事業化の準備を行い、2020年の4月に事業会社として設立する運びとなりました。
XPRIZE財団は、航空・宇宙系の人にはよく知られているんですが、学生時代に民間スペースシップで最初に宇宙に到達したグループに財団が賞金を贈るという賞金レースのニュースを見たこともあり、憧れもありました。2015年当時、私はマーケティング部門の海外ブランディング担当だったんですが、XPRIZE財団の方が「Google Lunar XPRIZE」に関連するイベントで来日することになり、ANAのロサンゼルス支店に航空券のディスカウント依頼が入ったんです。それを耳にした僕は、そこからきっかけをつくり、マーケティングモデルを考えてXPRIZEとタイアップさせていただくことができて。
その際に、財団の創設者であるピーター・ディアマンデス氏から、次の賞金レーステーマを公募するという話を聞いたんです。それまでXPRIZEの賞金レースのテーマは、財団に所属する物理学者や起業家らスペシャリスト集団が設計して、それにラリー・ペイジ氏(Google共同創業者)やイーロン・マスク氏(Tesla創業者)などの資産家、著名人が数十億円を投じて冠スポンサーをするといった形でした。
しかし、次の賞金レースはテーマの設計自体をコンペにするんだと。これはおもしろい、チャンスだと思いました。社内に戻って人事部や役員などに「このレースに業務外で参加したい」と伝え、現在アバターインで取締役COOを務めている梶谷ケビンとともにレースに参加しました。やるからには絶対に優勝すると決めていたので、ケビンと本業の業務後に夜な夜なアイデアを考えました。
 2016年米XPRIZE財団主催のコンペティションの際の写真
2016年米XPRIZE財団主催のコンペティションの際の写真
75億人の生活を変えるには
深堀レースの大きなテーマは「10億人の生活を変えられるかどうか」だったので、何だったら10億人の生活に変化を生じさせられるか、という視点で考え抜きました。ANAは多くの人に利便性をもたらしている素晴らしい会社だと思っていますが、エアラインならではの限界も実はありまして。
というのも、エアラインの利用者数は世界人口75億人中の6%しかいなんですね。同一人物が数回利用しているというのが現状です。だとすると、より速い移動手段を発明したとしても、結局は富裕層の乗り物になってしまう。そこで、一部の富裕層だけではなく10億人に訴求できることは何かを考え抜きました。
その結果、「身体を伴わない移動」つまり「テレポーテーション」に行き着きました。調査を進めると、既存のテクノロジーで物質の伝送までは叶わなくとも、情報を光の速度でテレポートさせることはできている。先述したように、「人間とは何か」を考えたときに、「身体」はマスト条件ではないはずです。瞬間移動体験は、限られた富裕層だけではなく多くの人の生活を変えられる。そう確信を持った僕とケビンは、実装に向けての歩みを進めました。
西村深堀さんは、ANA入社時は運航技術のエンジニアという技術畑の方ですが、最後まで一人でやりたいタイプのエンジニアではないですよね。
深堀はい、それは小さい頃から大切にしていることかもしれません。悪く言えば、いつも誰かを巻き込んでしまうというか……(笑)。最先端技術の追求は個人的にも大好きですが、それだけでは社会に実装させることはなかなか難しくもあるというのは常々感じています。
なので、自分の成功ですとか、起業家になりたい、大企業に育てたい、といった思いはあまりなくて、いかに社会にインパクトをもたらせられるか、が僕の中で一番大事にしていることなのだと思います。そのためには、アバターインはANAから独立してスタートアップという形で設立させたほうがいいと考え、今に至っています。
西村具体的に、なぜスタートアップという形のほうがいいと思ったんですか?
深堀大企業が全く異なる領域に参入するには、何かしらの取っ掛かりが必要です。世界中から各分野のエキスパートを積極的に採用し、アバターに関するサービスやテクノロジーのリサーチの強化、パートナー連携、外部資金調達などを通して、新規市場の開拓を行うためにはANA本体としてやるよりもスタートアップとしてやったほうが早く実現できます。
冒頭で少しお話したように、XPRIZE財団のレースでグランプリを取った後、ANAが運営主となり「ANA AVATAR XPRIZE」というロボティクスの賞金レースを創設したんですが、それもやはりより早く社会実装を進めたかったからです。81カ国、820チームが参戦したその賞金レースを通じ、世界中のエンジニアのネットワークができたら、多くのエンジニアが突き当たる壁も見えてきました。みんなが困っている「突破できないテクノロジー」を突破していくことを重視すると、やはりスタートアップという形のほうが適していたんですよね。
最先端テクノロジーの探求と社会実装のバランス
西村2018年頃のアバタープロジェクトの際の実証実験では、超遠隔での同期などの最先端のロボティクスも扱っていましたよね。一方で、「ニューミー」では、今すぐできる、かつ、一番やるべきことという感じでグッと機能を絞ったと思うんですね。研究開発機関じゃなく、スタートアップとして何をやるべきかに。僕は自分だったら、その切り替えが難しいなと思って。やっぱり最先端に触れているとすごく楽しいから、そっちで研究所をつくりたくなってしまいがちというか。
深堀私もエンジニアなので、その気持ちはすごくよくわかります(笑)。エンジニアが集まるとどうなるかというと、「ASIMO(アシモ)を超えようぜ!」となっちゃうんですよね。ただ、エンジニアたちも徐々に「高性能が必要なわけではなかった」とわかり始めています。というのも、アシモにしろ、トヨタのロボットにしろ、既にめちゃくちゃ高性能なんですよね。今まで国をあげて開発に取り組んできた災害救助系のロボットにしても同様です。ただ、それだけでは社会に浸透させることはできない。
本当に社会実装するためには、やはり大量の人がサービスとして使わないと、技術の改善もできないし、結局市場自体もできないというのが冷静に客観視したときに僕が感じたことで。これは「beam(ビーム)社」から学んだことでもあります。ビームはさまざまな大学との共同研究のもとつくられた「PR2」(腕や手がついた高機能ロボット)をつくったウィロー・ガレージ氏が創業者なんですね。
でも、ビーム社を訪れると、パーソナルロボット「PR2」からだんだん腕などをなくしていったロボットがあるんです。僕もアバターを実装している中で、はじめのうちはよく「動くiPadじゃないか」といったことを言われたんです。けど、僕らがしたいのはカッコいいロボットをつくることではなくて。なぜなら、現段階において、ロボットは結局ロボット好きしか購入していないじゃないですか。残念ながら、ハイテク系に興味がある人だけが買っているのが現状です。
一方で、僕にこだわりがあるのは、「誰でも使える」という点なんですね。興味がない人も使っている、という状況です。言ってしまえば、今のスマホのような感じにしたいという思いがすごくあって。であるならば、やはり現実をきちんと見なければなりません。なぜなら、興味のない人にロボットを本当に使ってもらうことには非常に高いハードルがある。
例えば、高齢者や単身赴任者の自宅に置いてもらうと、最初は倉庫に入れられてしまうということも実証実験の際にたびたびあって。倉庫じゃなくとも、壁に向けて置かれるですとか。ただ、これが1ヵ月経つとリビングに置かれ、3ヵ月経つと「お金を払って購入するから、持って帰らないで」といった具合になるんです。数ヶ月後にはアバターネイティブの子どもたちが「手が欲しい」と言い出したり。
つまり、はじめはロボットに興味がない人たちに利用してもらうためには、ステップがあるということです。アバターインには世界屈指のトップロボティクス研究者が集まっているので、「PR2」のようなロボットもできることはできるんですよ。ただ、広く使ってもらうためには、その機能は最初は足かせになってしまう。加えて、普及に至るまでは莫大な費用や認知度を駆使し、無償で広めるくらいのことをやらなければ、ロボットなんてそう簡単に社会実装されないというのが現実なので、僕らはそこに挑戦しています。
具体的な例として今ニューミーが使われているのは、百貨店の売り場や養護学校、介護施設、医療施設などです。ダイヤモンド・プリンセス号に乗船していた新型コロナウイルス感染症の患者さんが入院した病院にもいち早く試してもらいました。医師はクリーンルームからの経過観察が可能になりますし、入院中は家族も会えないからアバターで会って毎日見守りたいといった声もいただきました。
そうした人たちがロボット好きかといえば、まったく違う。「aibo(アイボ)」も「LOVOT(ラボット)」も持っていないという人たちです。でも、いいんです。むしろ、そういった人たちが毎日使ってくれることが重要で。それこそ、アバターを動かしたいからスマホを買ったというおじいちゃん、おばあちゃんもいるくらいです。さらに、より身近に感じてもらうために「ゲゲゲの鬼太郎」カラーの試作品をつくってみたりといろいろ試しています。
使う人がいるからこそ改善される
西村ちょうど夏前くらいに、ROOMの連載でも登場いただいた京都大学総合博物館の塩瀬隆之さんとアバターイン社でプロジェクトを立てようとしたんです。で、それはタイミングの問題やたまたまその時は叶わなかったのだけど、ちょうど先日、塩瀬さんが学生たちと自分たちでできるものをということでプロトタイプを作られて、新しい博物館鑑賞の実験に取り組まれました。
先ほど、「みんなが使えば技術が改善される」という話をされましたが、それはすごく重要だなと思って。研究所で改善するのではなくて、みんなで使うからどんどん改善されていくと。従来の考え方では、やっぱり研究所の中で開発して改善してとやっていましたが、そうではない。使う人がいるから生まれていく。
深堀賞金レースのために、トップロボティクスの研究所などをかなり訪問したんですが、平気で「10年経ってもまだラボから出ていません」と聞くと考えさせられますよね。その思いは、そこで働いているエンジニアの人たちにも共通すると思います。僕らは必要な機能がまだ足りていなかったとしても、プロトタイプでも世に出すんですね。大企業だったら、まだこのレベルでは出さないだろうものでも、まずは世に出す。それが僕のポリシーで。なぜなら、昔のパソコンやiPod、初期のスマホなども、今から考えたら微妙なものばっかりだったと思うんです。
でも、使う人たちがいてどんどん改善されてきた。そうしないと市場はつくれません。なので、それはやっぱりやっていかないといけないことだと思っています。あとは、いきなり災害時のためだけのロボットに取りかかるというのも順番として間違っていると思っていて。やはり、実装が先にあってからこそ、そういった状況下で現実的に使用されるのだと思います。コロナ禍でのニューミーの使われ方を見ていると特にそう感じますね。
使われていくうちに、どんどん必要な機能が判明してくるので、より誰でも使える形にしていけます。
西村そうすると向こうでやってみた経験が今度はまたアバターインに返ってきますよね。みんながやってくれるから「なるほど、そうなるのか」を先取りできると思って。
深堀その通りです。「ANA AVATAR XPRIZE」を主催したのも、そうした意図がありました。今まで、それぞれのスタートアップがさまざまな方法で介護作業や日常作業をロボットで試してきました。その知見の集積によって足りない技術や課題が見えてきます。僕らがつくっているロボットは、ロボットだということを忘れてもらう、という点を重視しています。なので、あえてムダな要素をつけているんですよね。
遠隔で動くものをつくるのは、難易度が高くない。iPadを基盤にしてもいいと思いますし、ラジコンにスマホをつければいいんじゃないかなどと思うんですが。そういったものとアバターが大きく異なるのは、アバターはユーザーが入っているときに「その人がそこにいる」という感じをいかに出せるか、なんですね。その際には「ムダ」が重要になる。
というのも、人間にはムダが多くあるんです。ニューミーではそれを再現するために、フラットな設計にせずに、あえて奥行きをつけるなどしています。これがディスプレイだけだと、単なる家電として認識しちゃうんですよ。
西村なるほど。
人間は「ムダ」だらけ
深堀海外のテレプレゼンスロボットは平らなものが多いんですが、実証をやっているうちにそこが課題だと気づいて。あとは、アバターショッピングをしていると、店員さんはお客さんがどっちを向いているかわからないんですね。それに対して、技術的には魚眼レンズにしたら下も見えるんじゃないか、といった話になるんですが、それだとダメなんです。存在感の瞬間移動なので、ムダだらけでないといけない。
例えば、西村さんがぼーっとしながらブラブラ歩いていているとしたら、「ぼーっと」感が伝送されなければならない。「実際に横にいる」感じが伝わらなければ存在感の瞬間移動にはなりませんから。おもしろいのが、アバターだと無言が成り立つんです。人と人とが「そこにいる」のを体現するためには、言葉が絶対に必要ということはないですよね。
しゃべらなくても、同じ場を共有してなんとなく居心地がいい、ということってたくさんあると思うんです。オンライン会議ツールで存在感まで伝送できるかというと、それはまだ難しい。そのことは冒頭でお話した、生き物の前での実験からよくわかります。さまざまな実験や実証から、「人である」ということを認識するためには、いくつかの外せない要素があると判明してきました。
それが奥行きや背丈、ムダな動作などです。ニューミーも手がなかったり、二足歩行にはしていなかったりなど、確かにそぎ落としてはいるんですが、重要な要素は落とさず残しています。
西村『ベイマックス』というアニメ映画がありますよね。ベイマックスはムダに太い。機能としては邪魔なんだけどなんかかわいい、みたいな。
深堀まさにです。ニューミーの真ん中はクッションになっていて、いろんな形にできるんですよ。それはやはりある程度の丸みが帯びたほうが親近感を持ちやすいので、あえてそうしています。そうしたことも含めて、インフラにするためにはどのラインがいいかはかなり研究しています。
西村すごくおもしろい。そうすると、ロボティクスだけでなく、まったく違うチームも参画できるわけですよね。
深堀その通りです。心理やコミュニケーションなどの研究も必要になりますから。そこに関連して、僕らがおすすめしているのが、1台だけでなく2台からはじめるということです。1台だとただのロボットになってしまうのが、2台存在するとエコシステムというか、ソサエティになるんですよね。
西村パナソニックのaug labというロボティクスのラボラトリーがあります。そこで「babypapa(ベビパパ)」というプロダクトが最近つくられたんです。それは3個セットの小さいロボットで。子どもと向き合うロボットではなく、3体がしゃべっているところに子どもが入るという設定になっている。つまり、子どもが入れてもらうコミュニティなんです。子どもがいなくても、ずっと動いているというのがすごく大事で。
深堀いいですね。僕らも、もう少ししたら、ひたすらブラブラしているモードとかを出すと思います。
西村ははは、いいですね。「なんかヒマそう」みたいな(笑)。
深堀そういったところを目指しているんですよね。それを実現させるためには、バックエンド(ユーザーからは見えない後方部分)でかなりのスペックのエンジンが必要なので、面倒な部分まで細かくやっています。僕は自身がエンジニアでもあるので、一時的なイベントには終わらせたくないんです。そのためには、きちんと時間をかけてやらないといけないのことも多いので、そうしています。
人類は、もうそろそろ瞬間移動技術をインフラにしてもいい
西村どうやったら本当に実現するかが重要で、デモンストレーションしたいわけではないということですよね。アバターを着想してから5年ほど経ってみて、深堀さんの最初の思い「75億人に夢と感動を」という部分は、修練したり変化があったりしましたか?
深堀ほとんど変わっていませんね。アバターを世に出すタイミングも結構重要視していたんですが、たまたま今コロナというパンデミックで「コロナがあったからやっているんですか?」と聞かれますけど、そんなことはなくて。人類はもうそろそろ、こういう技術をインフラにしてもいいよな、というのは前から思っていました。
だって、SARSやMERSなどのウイルスによる感染症や、台風などの自然災害の度にモビリティがピタっと止まってしまうわけですよね。台風などは何十年に一回という頻度ではなく、年に何度も経験する。
僕らはそういうことを繰り返してきています。だからこそ、生身の体を移動させることがモビリティに必要なのかという問いはずっと持ち続けていましたね。それが冒頭にお伝えした、「人間=身体」なのか、「身体=私」なのか、という問いで。「身体が私」なのではなくて、「意識が私」ですよね。
なので、西村さんの意識をこちらに転送してアバターという体で動き回ったとしても、それは西村さんのままであって。たぶん、西村さんの思い出もそのロボットで動かして、こちら側の思い出になるはずなんですよね。そういう意味で、「一番速く移動できる瞬間移動モビリティ」だと思っていますし。
さらには、アバターは1対複数の場所に同時に存在することもでき、変身もできるテクノロジーです。小さくなったり、大きなパワーを出したりといったように。これからの時代は意識だけを瞬間移動する、というのもモビリティの枠組みに入ってくる。そのほうが、はるかに世界中の人たちはつながりあえますし、社会参画もできるし、好きな場所から好きなところで生活を送ることができます。
今後、アバターによって教育も大きく変わるんじゃないかと思っています。今年5月に種子島宇宙センターから「こうのとり」9号機によって打ち上げられ、現在、国際宇宙ステーションに「space avatar」が設置されているのですが、それを地上から操作できるイベントも行なっています。
 国際宇宙ステーションに設置されているspace avatar
国際宇宙ステーションに設置されているspace avatar
宇宙に限らず、例えば紛争地域などは、そこを訪れたことがない先生から「パレスチナとは」みたいなことを聞くのもおかしな話じゃないですか。アバターだと、パレスチナのアバターに入り歩き回って、その後イスラエルのアバターに入ってまちの人と話してくる、といったことが可能です。
アバターなのでアプリケーションで自動翻訳も可能となると思います。もはや、ニュースや授業でデモが起きていることを聞くなどの一方通行の教育ではなくて、自分から現地の人に会いに行き、今どういうふうになっているのかを体験する。アバターでデモに参加してみてもいいし、世界の人々がどのように感じ、考えているのかを体感できる時代です。
「戦争はよくない」ということを一方的に教えるだけじゃなくて、実際に紛争地域のアバターに入って、目の前で困ってる人をスルーするのか、助けるのかはあなた次第という世界になってくるのだと思います。
車の普及に見る、革命前夜のアバター
西村アバターが新しい革命だと感じたのが、今までの「感覚の移動」はテレビにしてもラジオにしても、向こうがこちらに来る形でしたよね。でも、アバターはこちらから向こうに行く。だから動ける体は必要で。それはすごい切り返しというか、これまでの逆です。
もう一つは、例えば今オンラインで仕事をするとなると、だんだん部屋がコックピットみたいになりますよね(笑)。家がコックピット化すれば、ある意味外に出なくてもいいから。出てもいいんだけど、出なくてもいい。そうなると、今までの時代がグッと戻って、その辺にあるものを取って食べていた狩猟採集の時代みたいなところに近づくと思って。
頑張ってきた時代から、家から全部行けるという時代に切り替わるなと。そういう切り返しをつくっていくのがこのアバターのおもしろいところだと思いました。
深堀そうですね。そこにはアバターという名前に込めた思いも関係しているかもしれません。最初は、周囲からすごく反対されたんです。それでも、社名にも「アバター」という単語を入れたのは、映画で『アバター』ってありますよね。あの世界を意識していて。
X PRIZE財団のコミュニティに監督のジェームズ・キャメロン氏もいたのですが、あの映画では主人公がまったく別の生物の体に接続して、最後はその生物の文化まで共有して生きていくわけじゃないですか。それこそアバターの究極形だと思うんです。そういう世界観をイメージし、目指しています。
西村今日ずっと話を聞いていて思ったのが、アバターインはロボットの会社ではなくて、概念を少しずつズラしたり、融合させていったりしている会社だということです。その概念がしっかりしているから、次に必要な部分が拓けていくんだと思います。深堀さんのお話を聞いていると、車が爆発的に広がったときのことが思い浮かびます。
自動車が最初につくられたのは250年ほど前なんですが、広まったのはそれから140年ほど後の1900年初頭です。普及の引き金になったのが、ヘンリー・フォードが生み出した「T型フォード」なんですが、車自体はそこから100年以上前にできていた。でも広まるには至らなかったと。
そこで注目すべきなのが、「T型フォード」は最先端テクノロジーは搭載されていないという点です。むしろ、最先端の真逆を行く最小限の機能でつくられている。だからこそ、とにかく量産できた。
それで一気に市民にも普及したんです。それまではごく一部の富裕層の乗り物だったのが、5年間で爆発的に広まった。ニューミーはまさに車の例に近いと思って。ロボットに関して、テクノロジーとしては既に100年蓄積してきているから、かなりあると。ここからのスピード感はすごいとでしょうね。昨日なかった風景が突然広がるというか、革命前夜なのだと思います。
車もそうでしたが、アバターであれば暮らしだけではなく「まち」の形も変わると思います。例えば車の場合はガソリンスタンドや信号機が必要になって、法律という制度側も後追いでできて、といったように、平和に運用できる「まち」の形もできていくんだと思います。
身体的制約からの解放は、人類にとって希望であり進化
深堀そう思います。加えて最後にお伝えしたいのが、アバターはモビリティでは終わらないということです。モビリティの進化であるだけではなく、これはインターネットの革命でもあると僕は思っているんですね。というのも、今のインターネットに掲載されている情報は、すべてリアルタイムではなくて「過去に起きたこと」ですよね。でも、アバターがつくるインターネットはリアルタイムです。意識が飛ばせるわけですから。さらにその情報も、例えば私がロボットでブラブラしているような動きまでデータになる。
そうした特徴によって、例えばみなさんの中で料理が得意な方がいたら、家に置いているアバターにその人に入ってもらって、その時間「この料理を教えます」といったこともできるわけです。
医療に関しても同様で、他国から15分間だけ診察してもらうといったことも可能ですし、もっと言うとペン回しが得意な人がいたら、ペン回しのスキルを自分の意思で売るということだってできる(笑)。そのような形でのスキルシェアリングができたりと、アバターによって人々が支えあい、助け合うようなインターネットになってくると私は思っています。
西村いいですね。以前インタビューしたDabelの井口尊仁さんのお話を思い出しました。僕が携わってきた心理学の分野でもできることの可能性が大きいでしょうし、茶道や日本舞踊など日本特有の芸術・文化分野での可能性もすごく感じます。例えば、間合いは茶道が長けているし、所作は日本舞踊が長けている。
茶道だとしたら、ティーパーティーと茶道はやはり大きく違います。華道も同様で、フラワーアレンジメントと華道は別のものですよね。そういった日本独自のものが活かせる可能性があるから、アバターインが日本から興ったのは強みだと思います。
深堀そのあたりは研究を進めていきたいですね。僕はコミュニケーションが得意でない人も、アバターで入るとなぜか人とすごく仲良くなれる、といった世界をつくっていきたいので、間合いや所作など日本が独自に築いてきた文化から学べることは多そうです。アバターは新しい身体であると同時に、優しさや存在感を体現できる世界最大の人助けのネットワークが構築できるものだと思っているので。
西村いいですね。アバターによって、日本が1,000年間続けてきた文化の意味が活かせる気がします。非物質的なものである「心」がアバターだったら感じとれるのではないかと思いますし、いずれ「アバター供養」みたいなものも生まれるかもしれませんね。そうなったときには、人間が抱いてきた概念がひとつアップデートされるのだと思います。
深堀おもしろいですね。身体的制約からの解放は、人類にとって希望であり進化だと思うので、僕自身も今後の展開が楽しみです。

 この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/
この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/
エアラインだと人口の6%にしか訴求できない。75億人の生活を変えられるものはなんだろう、と考えに考え抜いた末に、既存の「移動」の概念に疑問を抱いた深堀さん。そこから「人間=身体なのか」という根源的な問いを深めていった経緯は、聞いていて興奮を覚えました。
ご自身もエンジニアであり、最先端技術の開発に胸躍らせる気持ちもありながらも、社会実装を可能にするためには、という視点を常に忘れずに行動し続ける姿勢にも感銘を受けました。お話を伺っていたら、ANAへの入社後からはもちろんのこと、幼少期からも「深堀流」の本質は変わっていないのだろうなと感じました。そしてこの先、遠くない未来に私は自宅で「深堀流」から生まれたアバターを使うことになるのだろうと思っています。
次回は、生体模倣デザイナーであり材料科学者の亀井淳さんに、気候変動が進展する時代において人が水と親しみながら暮らせる未来の可能性について伺います。こちらもどうぞお楽しみに!