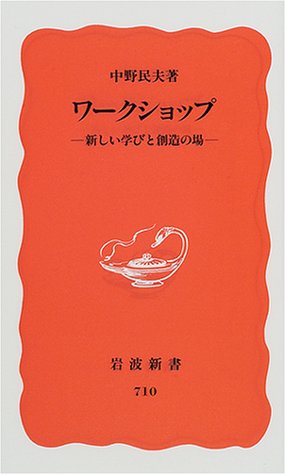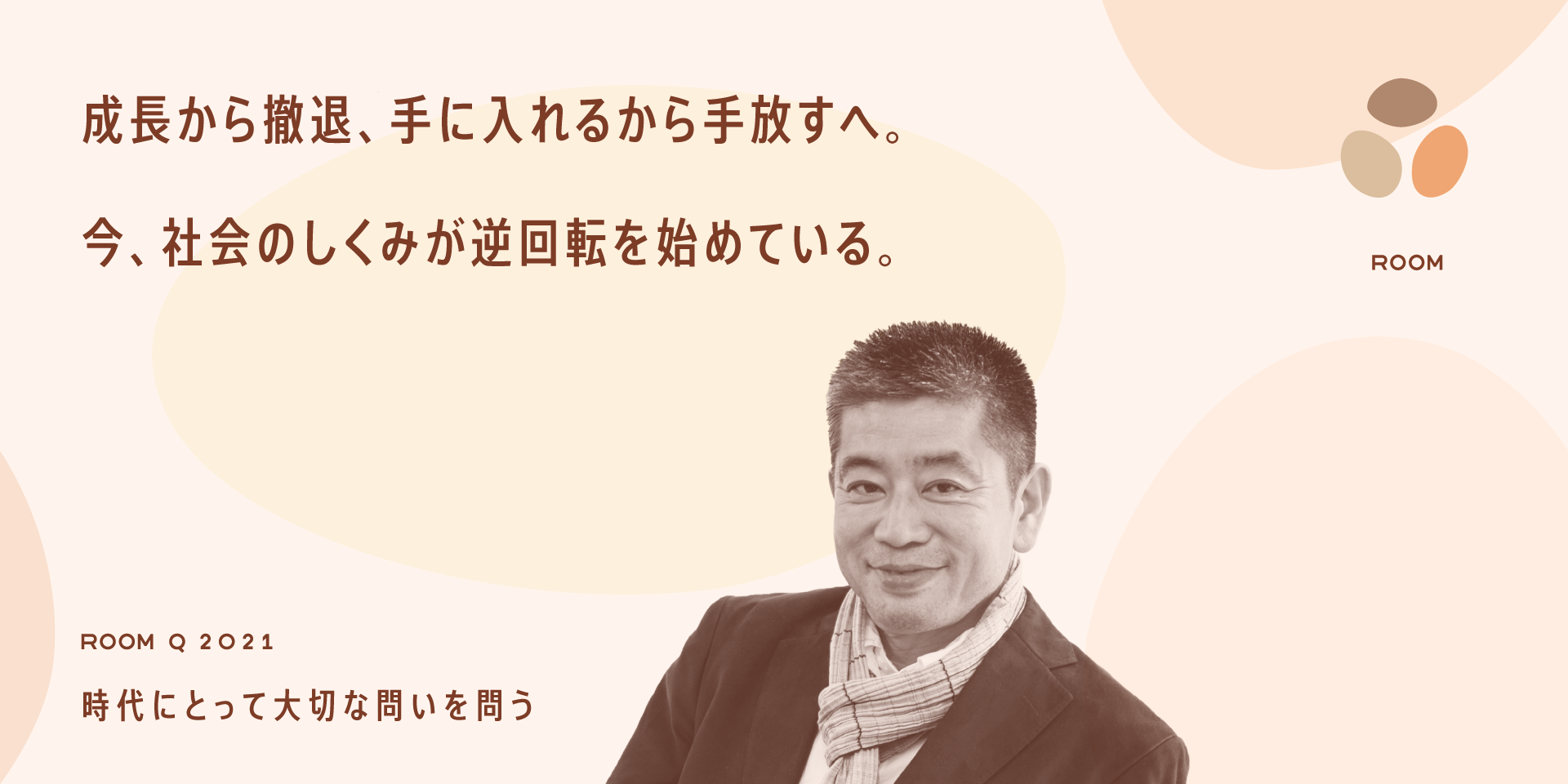なぜ、ひとつの地球に生きる仲間だという感覚を持てないんだろう?東京工業大学教授・中野民夫さん【インタビューシリーズ「時代にとって大事な問いを問う」】
シリーズ「時代にとって大事な問いを問う」は、ミラツク代表・西村勇哉がインタビュアーとなり、「時代にとって大事な問い」を問う活動をしている人たちにお話を聞くオリジナルコンテンツ。シーズン1の10回を終え、シーズン2に入ります。
今回は、東京工業大学教授でワークショップ企画プロデューサーの中野民夫さんにインタビュー。博報堂時代に休職してカリフォルニア統合学研究所(CIIS)に留学した時にジョアンナ・メイシー氏に学び、「ワークショップ」や「ファシリテーション」を日本に紹介してきた人です。
インタビューは、中野さんが少年の頃に見ていた、1960年代の東京の風景を語るところからはじまります。政治の季節、猛烈サラリーマン時代、カリフォルニアで出会った「ワークショップ」。人と人、人と自然、人と自分自身をつなぎ直していく中野さんと、「ダイアローグ」に可能性を感じていた西村さんが出会うのは2009年のことでした。世代を超えてつながったふたりの問いと対話の時間を、この記事でみなさんと共有したいと思います。
(構成・執筆:杉本恭子)
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授/ワークショップ企画プロデューサー
1957年東京生まれ。東京大学文学部卒。博報堂に30年勤務したのち、同志社大学総合政策科学研究科教授を経て、2015年秋より現職。1989年、博報堂を休職してカリフォルニア統合大学院研究所(CIIS)で組織開発やワークショップを学ぶ。以後、人と人・自然・自分自身をつなぎ直すワークショップやファシリテーション講座を実践。主著に『ワークショップ』(岩波新書)、『ファシリテーション革命 参加型の場づくりの技法』 岩波書店(岩波アクティブ新書)、『学び合う場のつくり方――本当の学びへのファシリテーション』(岩波書店)など。
1964年の東京五輪を見たのは、小学校1年生のときだった
西村まずは中野さんのこれまでの経緯を伺いたいと思います。どこからはじめましょうか。
中野今、63歳になります。子どもの頃は、中庭に大きな泰山木(たいさんぼく)がある、東京・赤坂の5階建アパートで暮らしていました。物心がつくころの東京はオリンピックに向けてあちこちが工事中で、高速道路や新幹線ができて、戦後の街がどんどんきれいになっていきました。テレビが普及して『鉄腕アトム』がはじまって、「未来はどんどんステキになる」という空気に満ちていた。
 中野さんが小学校1年生の時に描いた、オリンピックの聖火台に点火している絵(中野さん提供)
中野さんが小学校1年生の時に描いた、オリンピックの聖火台に点火している絵(中野さん提供)
1964年10月10日、東京五輪の開会式の日にブルーインパルスが五輪の輪を空に描いたのを見あげた日も覚えています。小学校1年生でしたね。国立競技場も近かったから、競技もけっこう見に行っていました。1960年には、六本木にあった防衛庁に「安保条約反対」のデモで人が溢れるなか、子どもたちは電車ごっこしながら「安保条約反対!」と言いながら走っていた。
当時の東京は、楽しくてすごく少年の心を掻き立てるまちでしたが、一方では新宿に行くと戦地で手や足を失った傷痍(しょうい)軍人さんがいて、戦後の影も色濃く残っていました。あと、少年時代といえば野球ですね。
杉本やはり、巨人ファンだったんですか?
中野はい。日本シリーズを9連覇したV9時代(1965〜1973年)だったから、巨人・ヤクルト戦で面白くなりそうだと、母と一緒に神宮球場まで走って見に行っていました。小学校5年生のときに、父の転勤で山口・下関市に引っ越したのですが、中学2年生の3学期にまた東京・中野に戻りました。高校編入した麻布高校は、学生運動が盛んだったあとで、自由な雰囲気でした。学園祭はすごく派手で面白かったけど、真面目にやることをバカにする風潮もあって、僕はあまりなじめませんでしたね。
ただ、高校2年生のときに赴任してきた倫理社会(哲学)の先生が、カントの話とかをしているのに妙に耳が立って。その先生の周りに集まる変わり者たちが、土曜の午後に自主ゼミをやるようになりました。受験や単位のための学びではなく、それぞれが明治以降の日本の思想家について調べて発表し合うという場があったんですね。僕のワークショップの原点となる「学び合う場の楽しさ」は、あの先生と仲間たちとの場にあると後になってから思いました。
学歴社会を内側から変えようと東京大学へ
杉本中野さんが大学に進学されたのは1977年。まだ学生運動の熱が残っていた時代だったのではないでしょうか。
中野あと10年早く生まれていたら、間違いなく敷石を剥がして投げていただろうし、僕もまた革命を起こしたいと思っていました。「まずは学歴社会を中から変えるぞ」と、その頂点にある東京大学に浪人して入学したのですが、授業は大教室ですごく期待外れだった。
学生運動や演劇の拠点になっていた学生寮・駒場寮なら、熱く哲学を語り合う青春があるんじゃないかと思って入寮したけど、当時はもう内ゲバがひどい時期でね。「もう左派には道がないな」と思いはじめた頃、社会学者の見田宗介さんが「真木悠介」というペンネームで『気流の鳴る音ー交響するコミューン』(ちくま学芸文庫)を出したんです。見田さんは「今は右か左かの時代ではないでしょう。それぞれの井戸を掘れば必ず下で何かがつながりあっている普遍の世界がある」と、「上か下か」みたいな問いの立て方をしていて、面白いなと思いました。
受験体制のなかで「勉強しないと負け犬だ」と頑張ってきた自分を解き放ちたくなって、一年生の夏に休学。浜松のホンダの工場で期間工をしてお金を貯めて、自分を解き放つための旅に出ました。島尾敏雄さんが「ヤポネシア」という造語で日本列島を太平洋の島々のなかに位置付けたことに倣って、台湾から香港、インドシナ半島へと2ヶ月半くらい南下していったんです。ところが、ミャンマーで体調を崩してしまってね。20歳の1月15日に、ミャンマーの奥地でうんうん唸っていて「これが俺の成人式なんだ」と思ったのをすごく覚えています。
杉本それは一生忘れられない成人式ですね。
中野帰国してから、もう少し勉強し直して世界を見る視点をもとうと思って復学し、ワンゲル部で野外生活の技術を鍛えたりしました。この前ネパールのトレッキングに行ったときのことを思い出したんだけど。僕は体力があったから「チト、チト(早く、早く)」とみんなを急かしていたら、現地のシェルパ(ガイド)は「ビスターリ、ビスターリ(ゆっくり、ゆっくり)」と言って、呆れてたんだよね。でも、雄大な景色のなかを2週間くらい歩くうちに「こんなに空が青いのに、山や川が美しいのに、なんで急いでいるんだろう」って気持ちになってきたの。そしたら、最終目的地に近い標高4,200mのところで、僕が高山病で意識不明になってしまったんです。
子どもの頃から常にゴールに向かって先へ先へと競い合うなかで育てられて、それが習い性みたいになってしまっていたけど、高山病で倒れて「今、ここを味わう」ことが少しわかるようになったんです。
「浮世の最前線でネクタイ菩薩になろう」と博報堂へ
西村なかなか、僕が生まれる時代にたどりつきませんね(笑)。
中野このペースでいくとちょっと長くなっちゃうな(笑)。少し飛ばすね。
「今、ここを味わう」ということに興味が向いたときに、「東洋のものに何か大事なものがあるんじゃないか?」と思いはじめて。近くの禅寺に坐禅しにいってみたりしたんだけど、足が痛いだけで心が穏やかにはならなくて。星川淳さんがすてきな訳で日本に紹介しはじめていた、バグワン・シュリ・ラジニーシというインドの神秘思想家の本を読んで、非常に自由を教えてくれると思って感動したんです。
3度目にインドに行ったとき、ムンバイにあったラジニーシのアシュラムで約2ヶ月修行をしました。ただ、弟子になるには「ヒンドゥ名をもらう」「オレンジ色のローブを着ける」「グル(指導者、ラジニーシのこと)の写真が入ったペンダントを身につける」という3つの神器があったのね。僕はそれには抵抗があったから、オフィスに「なぜ必要なのか」と質問をしたら、「人は忘れやすいから、一瞬一瞬を生きると決めた証に必要なんだ」「いや、僕はその3つのしるしをつけずに頑張りたい」と言い合いになってね。
 1979年、中野さんがネパールで撮影した子どもたちの写真(中野さん提供)
1979年、中野さんがネパールで撮影した子どもたちの写真(中野さん提供)
ラジニーシは、「今ここ」に目覚め一瞬一瞬を生きることが大事であり、誰かのの思想に服従する必要はないと「I am the gate. Pass through me」(私は門だ。通り過ぎて行け)と言っていましたが、そのとき僕は「わかった、グルが言っていたのはこれだ。師にすがるのではなく通り過ぎていけということなんだ」と思ってアシュラムを出たの。「俺は最後の公案を抜けたぞ」 と意気揚々で、すごい自分が開いた感覚があって。ところが、アシュラムを出て南へ移動していくうちに、だんだん体がだるくなって。ポンディシェリという町の病院に、肝炎で2ヶ月くらい入院したんですよ。
病院で横たわっているときにいろいろ考えてね。当時の日本社会は、世界から「エコノミックアニマル」と言われて、「過労死」が世界語になる高度成長の時代で。その裏側で、世界を収奪しているという思いもあったから、「一生ネクタイなんかするもんか」と思っていたんです。でも、そのときは「もうどこに行っても大丈夫だ」みたいな気持ちがあって、逆に企業に入って中から変えてやるんだという思いが湧いてきてね。その1年後、就職活動の面接で好きなことを言っていても内定をくれたのが博報堂でした。
「ここは言いたいことを言っていてもやれる世界かもしれない。何か新しい価値を世に提案できるかもしれない」という思いで、「浮世の最前線でがんばるネクタイ菩薩」を目指して、博報堂に入社しました。「今どきの菩薩は、お寺や山ではなくて、ネクタイを締めなきゃいけないような既成社会の中でこそがんばらないといけない」と考えていたんです。
モーレツ営業マンが「ワークショップ」に出会うまで
杉本博報堂には何年くらいいらっしゃったんですか。
中野3年ぐらいのつもりだったのに、30年も勤めました。入社したときは「知らないところに行きたい」と大阪に赴任して5年半いました。東京に転勤してからは、毎日終電まで働くモーレツ営業マンだった時期もありましたね。深夜2時くらいまで仕事をしていたある夜、信頼していた先輩に「中野、お前こういう仕事は本当に面白いか?俺たちの仕事は終わりがないだろ。俺は飽きたし疲れたよ」って言われたんです。
僕はサーっと血が引いて「モーレツ営業マンになるために入社したわけじゃなかったよな」と、初心を思い出しました。「これは仕切り直さなきゃ」と思いました。トランスパーソナル心理学などを日本に紹介していた吉福伸逸さんに「今もカリフォルニアは面白いですか?」と尋ねたら、いくつか面白い大学を教えてくれました。そのひとつが、のちに留学したカリフォルニア統合大学院研究所(CIIS)です。
著書『ワークショップ』(岩波新書)の冒頭にも書いたけれど、授業見学に行ったらみんなが床のクッションの上に輪になって座っていて、「入れ入れ」と招かれてね。英語もできなかったのに「来て一緒にやればいいよ」と言ってくれたんだよね。
当時の博報堂には、休職して留学する制度なんてなかったけど、わりと一所懸命働いていたから周りの人に話を聞いてもらえる関係性はありました。「アメリカの大学院に行きたい」と先輩に話したら、部長から局長へと話が伝わって、企画書のような休職願を7枚くらい書きました。今でも覚えていますね。「これからのキーワードは地球環境問題。モノ・カネ・情報だけではなく環境を視野に入れないといけない時代がくるから、博報堂も準備をしておくべきじゃないか。そのために、先進地域のカリフォルニアで学びたいから2年間休ませてほしい」という内容でした。
留学したのは1989年。日本では公害問題は認識されていたけれど、地球全体の環境問題についてはまだ言われていない時代でした。留学中に湾岸戦争が起きて、サンフランシスコ周辺では反戦運動の波がすごかった。僕たち日本人は「バークレーKAI」というグループをつくって、その様子を日本に伝えたりしていました。そのなかに、ティク・ナット・ハンの翻訳をしている棚橋一晃さんがいたんです。

 1990年1月17日、サンフランシスコ証券取引所前にて座り込む戦争への抗議運動の市民と公道の占拠を理由に排除を伺う警官隊。「この後、私を含めて数百人が丸ごと逮捕されたのですが、非暴力で皆おとなしく静かに逮捕された」と中野さん。(中野さん提供)
1990年1月17日、サンフランシスコ証券取引所前にて座り込む戦争への抗議運動の市民と公道の占拠を理由に排除を伺う警官隊。「この後、私を含めて数百人が丸ごと逮捕されたのですが、非暴力で皆おとなしく静かに逮捕された」と中野さん。(中野さん提供)
反戦運動は、怒りをあらわにして闘うんだけど「内なる平和と外なる平和はつながっているんじゃないか」ということで、ティク・ナット・ハン著『Being Peace』(のちに中公文庫から翻訳が出版された)の読書会をはじめました。ティク・ナット・ハンはベトナム出身の禅僧で、ベトナム戦争中に被災者や難民のために行動した平和活動家でもあります。「Peace in every step.(平和は一歩一歩のなかに)」と語り、敵対者を弾劾しても本当の解決にはならないというんですね。
自分(self)という観念を広げていくと、万物のつながりのなかで生かされていることが感じられて、“無関係な人”なんていない。自分を深めながら社会に関わっていく、社会変革とスピリチュアリティを統合していくような道を見出したんですね。CISSの修士論文では、自分の平和運動・環境運動として、「つながりを取り戻す」「今ここを大事にする」「みんなが心から話せる場をつくる」という3つを大事にしたワークショップをやっていくと書いたのですが、今に至るまでずっとやってきているなと思います。
博報堂で「心ある仕事ができた」と思えた90年代のこと
西村ようやく90年代に入りましたが、まだ僕は大学生になっていないですね。
中野そうか。90年代後半から、日本企業もようやく地球環境室などを置くようになり、97年には京都で地球温暖化に関する国際会議があって京都議定書が採択されました。その時期、精神論や倫理観で「地球環境を守ろう」というだけではなく、トヨタがプリウスを発売してビジネスの世界でも環境問題が扱われるようになったのは、すごくインパクトがあったと思います。特に、少し前までは、広告会社では「環境なんて気にしていたらモノが売れなくなる」なんて言われた時代でしたから。
同じく97年に、山梨県で県民啓発のための環境フェスティバルという事業があり、僕らは気合を入れてコンペに勝ちました。それが、「内側からなんとかしたい」と博報堂に入社して15年後に、初めてできた心ある仕事でした。その頃から「中野が環境に詳しいらしい」と知られるようになり、少しずつやりたい仕事をやれるようになっていきました。
その次に大きかったのは、“自然の叡智”をテーマに、121カ国4国際機関が参加した2005年の「愛・地球博」です。初めて万博のなかに市民参加を取り入れて、NGOビレッジの地球市民村と市民参加パビリオンという2つのプロジェクトが計画されました。僕らは地球市民村を企画し、参加団体を公募して、時間をかけて準備したのですが、会社では「NGOって反対運動のやつらだろ。得意先に迷惑がかかるんじゃないか」なんて本当に言われてた時代のことです。

 2005年愛知万博地球市民村(NGO Global Village)のようす(中野さん提供)
2005年愛知万博地球市民村(NGO Global Village)のようす(中野さん提供)
 愛知万博地球市民村最後のファイナルコンサート(中野さん提供)
愛知万博地球市民村最後のファイナルコンサート(中野さん提供)
やっぱり、それまでの社会変革は闘いでしたよね。おかしなことに対して声を上げても、国や企業が間違いを認めなかったために、水俣病や四日市ぜんそくなどの公害が広がったわけです。それに反対するには闘いにならざるを得なかったという、日本のつらい社会運動の歴史があると思います。
愛・地球博は4年間をかけて準備をして、持続可能な開発は世界の課題なんだということを伝えるとともに、「反対運動」ではないということをわかってもらうためにも「持続可能性への学びの場」というコンセプトで、NGOビレッジを博覧会協会の主催事業としてやりました。僕らは、コンテンツを毎月全部入れ替えていたから、リピーターもすごく多くて。新聞報道が175件も出る話題の場になりました。
社会変革の方法論が変わっても世界の分断はなくなっていない
中野やっと僕と勇哉が出会う時代がきたかな?
杉本おふたりはいつどんなかたちで出会ったんですか?
西村そもそもは文希(あや)で、当時はまだ結婚していませんでしたが、彼女の家に民夫さんの『ワークショップ』があって借りて読んだんです。その後、ミラツクの元になる取り組みをはじめたときに開いたイベントの基調講演に来ていただいたんです。「未来をつくるワークショップ」というタイトルで、ミラツクの名前の由来になっています。タイトルが長いので、仲間内で「ミラツク」って呼んでいたんですよね。
杉本じゃあ、ミラツク誕生の瞬間に、中野さんにも立ち会っていただいていたんですね。
西村そうです。2009年でしたね。僕にとっては、「本で読んだすごい人を呼ぶ」みたいな感覚がありました。
杉本中野さんが経て来た長い道のりについてお話をうかがったのちに、27歳の西村さんが「ワークショップやファシリテーションのお話を聞かせてください」というシーンに至って、ふたりの間に受け継がれたものがあるのを感じます。
西村だんだん現代に近づいてきたので、インタビューのテーマである「時代にとって大切な問いを問う」について聞いてみたいと思います。今日お話を伺って、中野さんが積み上げてきたなかで感じている「今」と僕が感じる「今」は違うんだろうなと思います。中野さんが見ている「今」という時代に大切な問いってなんでしょうか?
中野1968年にアポロ8号の宇宙飛行士が、月から見える地球の写真を撮影し、「宇宙から見たら国境は見えないんだ」「本当に薄い大気圏、雲のなかにある水の惑星に生かされているんだ」と多くの人々が実感できたはずでした。でも、50年経っても、世界ではますます分断が進み、相変わらずさまざまな戦いがあって、すごく残念ですね。この同じ地球に生きる仲間なのに、SDGsや環境問題、平和や格差や差別の問題をなぜもっと共有できないのかな?と思います。
 Photo of the Earth taken from Apollo 8, called Earthrise (1968). /Bill Anders, Public domain, via Wikimedia Commons
Photo of the Earth taken from Apollo 8, called Earthrise (1968). /Bill Anders, Public domain, via Wikimedia Commons
アメリカで、ネイティブアメリカンのメディスンウーマンを呼んで「スウェット・ロッジ(浄化の儀式)」を体験したことがあります。「まず私たちの世界観をお話しします」と最初に語られたひとことが「We are all children of the earth.(私たちはみんな地球の子どもです)」でした。ビリビリと衝撃が走りました。そのことを、私たちみんなが深いレベルでもっと実感できれば、環境や平和の問題もずいぶん好転すると思います。僕は、環境や平和の問題に取り組む手段としてワークショップやファシリテーションをやってきたし、同じ地球に生きている、「みんな地球の子どもたち」という感覚を取り戻す仕事をしたいと今も思っています。
西村問題を解決する方法論についてちょっと伺ってみたいです。60〜70年代の社会運動は二項対立的で分断を生みやすかったという反省もあって、分断をつくらない方法を模索していったんだと思うんですね。でも、方法論は変わっても結局、分断そのものはさらに深まっています。何か足りないことがあるからなのかな?と思うんです。
中野たしかに方法論は変わってきたと思います。闘いに精力を使うよりも「自分たちのほしい未来はつくろう」というオルタナティブな動きが、greenz.jpの鈴木菜央くんあたりから明確に出てきましたよね。企業も、今や各社が競い合うようにSDGsバッジをつけて、ポーズだけではなく本業で勝負しようという時代になったことに希望を感じるところはあります。
じゃあ「社会は変わったのか」というと、「変わった」とは言えない感じがします。日本は言葉では「人間は自然の一部ですね」というとうなずく感じはあるけれど、本当に食べ物やエネルギーの循環に配慮して生活しているかというとそうではないでしょ。
つくづく自分自身のことも含めてですが、人間ってやっぱり自分で相当に痛い目にあって懲りないと変わらないんだと思います。今は、気候変動の問題にしても新型コロナウイルスの感染拡大にしても、懲りてもいい状況に近づいていると思いますが、すでに手遅れに近い状況になっていますよね。でも、人間の性としてしょうがないのかなあ。
ダイアローグとディスカッションの違いに核心がある
中野今日、勇哉と「ダイアログとディスカッションは違う」ということを話してみたいと思っていて。デヴィッド・ボームは、「ダイアログには決まった目的や課題はない」とも言っているよね。自分の言葉を他の人はそのままの意味では受け取らないけれども、自分が言いたかったことと相手が受け取ったことのズレを見ることで、お互いに共通する新たな視点を発見できるかもしれない。ダイアログは、すごく「創造的な営み」なんだとボームは言ってくれています。
学生でも「グループディスカッション」という言葉になじんでいる人たちは、「正解やいいこと、正しいことを言わなければ」という緊張があって口が重たくなるし、「批判から入ったほうが賢く見える」という感じ方もあって。それと、僕らがやろうとしているダイアログ、対話は違うんだと伝えたいんですけど、まだまだ孤軍奮闘なんですよ。

人と人が話すときに、正しさや強さ、結論を求めることに走るのはもったいなすぎると思う。国の議会、企業の会議、あるいはコロナ渦をめぐるテレビ番組の議論なんかも、正しさを論じ合うばかりで、一緒に何かを発見するコミュニケーションにはなっていないと思うんです。創造的な対話では、自分の思い込みや意見を率直に話すと同時にそれにこだわりすぎないでおく、ボームのいう「想定の保留」が大事なんだけど、それができないというか。
立場がある人は、「立場を守らなければいけない」「意見を変えてはいけない」と思いがちです。そのマインドセットを緩めて,「自分にはこう見えているけれど、そう見えていない人もいる」というふうに自分の枠を広げて、思いやりや寛容を育んでいかなければいけないと思うのだけど、その道はまだまだ遠い気がします。
西村ここ数年の感覚では、ダイアログのプロセスで見えたことをもとに「まずはこれをやってみよう」という行動に入ればいいんじゃないかと思って、自分たちもそう行動してみているんです。クライアントとの仕事でも「結論はわからない」と最初に話しています。でも、途中で何をやるかはわかるので「こういうふうに旅をしよう」ということはわかっていくんです。プロセスのなかで「結論は常に出つづけている」。ダイアログは「結論が出ない」ではなく「結論に引きずられない」んだと思っているんですね。
世間には、「ダイアログは生産性が低くて何も決まらない」「ディスカッションの方が生産性が高くて決まることがある」というイメージがある気がするのですが、実はダイアログはすごくたくさん決まることがあるのでめちゃくちゃ生産的です。瞬間ごとにどんどん結論が出るから、「やることが多すぎて全部やりたい」みたいな状態で終わるのがダイアログなのかなと思います。
むしろ、結論が常に出続ける創造的な話し合いがダイアログで、最後の結論だけを持って帰ろうとするようなすごく非生産的な話し合いがディスカッションなんだなと思っています。だから、いわゆる会議に出ると途中に生産的なところが全くないので本当に眠たいんですよね。良い話し合いはバンバン積み上がっていくから、無駄な会議を100回やるくらいの生産性がある。「創造的」というと「クリエイティブ」というイメージを持たれますが、ダイアログはすごく生産的なんだということがうまく伝わるといいなと思っています。
中野勇哉のその面白がり方がきっと伝わっているから、人がどんどん巻き込まれてきているんじゃない?
西村願わくば、その生産性を具体的に感じてもらえると僕はありがたいなと思っています。「どう見てもそっちの方がいいよね」と誰もが思えるような明らかな違いが出ているといいなと思います。
中野「べき論」でやろうとすると、頭では理解しても誰も行動をはじめないということが起きてしまうよね。やっぱり、すぐに難しい話題に入ろうとするよりも、アイスブレイクやチェックインに時間をかけて関係の質をあげる。すると思考の質が上がって、みんなが言いたいことを話していると自分がやりたいアイデアしか出てこないから、自然と行動もついていって成果が生まれる、ということは本当にあると思うんです。
すごい勢いで進んでいるのに、本質的にはブレーキを踏んでいる
西村今、中野さんたちが60代という世界に、僕らが生きているということは、一周回りはじめているのかなと思っていて。40年前であれば、中野さんが大学の先生で学生に批判される対象になっていたかもしれない。でも、世代が変わって、僕は20代の頃から上の世代と闘うようなシチュエーションに放り込まれたことはなく、年上の人たちと一緒にやっていくという体験をしています。今日お話を聞いていて、そこに少し可能性があるのかなと思いました。30年くらいかかったけど、ここからグッと加速できるかもしれない。
中野(嘉村)賢州とか勇哉が活躍しはじめて、人が集まるのを見て「新しい時代が来たな」と思っていたよ。勇哉たちはセンスも着眼点もいいんだけど、どうしたらいいかはあまりわかっていなくて。旗をあげるとみんなが吸い込まれるように集まってきて力を貸してくれる「真空」のようなリーダーシップ像はすごく新しいなと思っていました。「俺についてこい」みたいな強いリーダー像とは違って、みんなの内発的なコミットメントを引き出すじゃない?
西村そうですね。ただ、時代が良くなってきたかどうか、よくわからないなと思うんです。みんなが「良くしたい」と思って努力もしてきたけど「え?そっちに行っちゃうの?」みたいな感覚があるんです。
中野「良くなっていない」というのは、どういうときに感じるの?
西村日々のニュースにいい話がたくさんある日が全然なくて、手を替え品を替えいろんな大変なことが次々に来て、どんどんひどくなっていく。一方で、すごく困っているかというとそうでもない。じゃあもともとそんなに悪くなかったのか?と思ったり。ちょっとうまく言葉にならないんですけども。
自分の感覚としては、すごい勢いで世の中は進んでいると言われているけれど、ものすごい勢いでブレーキを踏んでいる感じもするんです。進んでいるかに見えるものが、全部止まる方向につながっているんじゃないかって。
どうでもいい世界で、どうでもいいことが、どうでもいい感じに大きくはなるけれど、本質的なところでブレーキを踏んでいるような感じ。たとえば、再生可能エネルギーの割合が増えていくのは良いと思うのですが、「再生可能エネルギー100%になったら何が変わるの?」みたいな感覚ですかね。本質的には、何も変わらないんじゃないかってちょっと思うんです。
中野テクノロジーによる飛躍的な進歩はあるけれども、世の中自体は変わっていないという感じなのかな。僕らが若い頃にアーネスト・カレンバックというアメリカの作家が『エコトピア』という小説を書いたんだけど読んだことはある? カルフォルニアとオレゴン、ワシントンの西海岸3州は、他州よりも環境への意識が高いから独立して「エコトピア」という国をつくるの。アメリカは西海岸と中西部の意識の差が顕著だから、非常にリアルな話だったんですね。
志向性が似ている人同士は共感しあえるし話もするだろうけれど、それ以外の世界との分断が深まるという傾向は相変わらず強いなと思います。
杉本中野さんは、学生時代も会社員時代も、そういった分断を目の当たりにして、「学歴社会を東大から変えよう」「企業の中から変えよう」、あるいは精神世界という「自分の中から変えよう」という、「中」を常に意識されていることが印象に残りました。分断を見つめ続けるのは非常に苦しいことだと思います。「分断をなくすのは無理かもしれない」と絶望することはなかったのでしょうか。
中野絶望はしまくりましたよ。もうどうしようもなく絶望したからこそ、ちょっとしたことが良く映るし希望も感じるというか。ファシリテーションの講座に来る人は、「話し合いを円滑にして活動を広げたい」とか、「社会を良くしたい」と思っている人が多いから、やっぱり希望を感じるよね。みんなすごい菩薩だなって思う。人間の社会は、より良き方向を模索して常に試行錯誤をしつづけているけれど完成はないんだよね。
この60年があったうえでの可能性とは?
西村最後にこれだけは聞いてみたいと思っていたことがあって。この60年の人生があったうえで、「ここに可能性があるんじゃないか」と感じていることはありますか?
中野組織の縛りがかなりゆるくなったことかな。副業や複業をする人も増えましたよね。高度成長時代は「会社に文句があるならやめろ」という感じだったけれど、組織の縛りが強くて本音が出せないというのは歪みが出ると思います。今は、それぞれが思っていることをちゃんと発言するほうが組織の活力になるという考え方になってきていると思いますね。
西村たしかに、それぞれが話せる時間は増えていると思います。会社とは違う名刺を持ってみるとか、そういうことが良い方向につながるといいなとは思いますね。
中野大きい視野で言うと、今地球上を生きている生物たちは、137億年の宇宙の進化の最前線を生きているわけじゃない? だから、いろんな人がいるけれど、みんな違った顔をした自分だというふうにも思える。みんながそれぞれに花開くことが、宇宙にとって一番ワクワクするうれしいことなので、みんながそれぞれの花を咲かせられたらいいなと思います。
企業も、社会に貢献しようと思って創業した会社が多いと思うけれど、やっぱり高度成長時代のなかで完全にお金に足を取られたと思う。ところが、右肩上がりはもう続かないんだという停滞を経験して、コロナ渦で人の移動が制限されて、今ようやく熱病から覚めるチャンスがあるのかなと思います。
ジョアンナ・メイシーも言っているけれど、大転換期には50〜60年かかるそうです。1970年代初めにオイルショックや公害が起きて「このままではいけない」とわかっていたのに、ようやく2020年になってSDGsを掲げるようになりました。50年かけてようやく折り返しているのを実感するところもあります。
若い時は一気に革命を起こしたいと思っていて、すぐに変わらない社会への苛立ちもあったけど、できることには限りがある。でも長く生きてよかったのは「振り返ると少しずつでも変わったことがたくさんある」と知れたことかな。いつの時代も困難はあるけれど、前向きに取り組む人が必ず出てくるから希望は感じています。
さっき、勇哉が「ダイアログの途中にたくさんの結論が出つづける」と言っていたよね。それと同じように、平和で持続可能な社会はある日パキンとできるわけではない。それぞれの現実に向けての小さなチャレンジやそこでの実感がね、ある意味では何かを実現しているんじゃないかと思います。
 愛知万博地球市民村の最後の夜、アースボール(地球)が人々の手から手へと渡った。(中野さん提供)
愛知万博地球市民村の最後の夜、アースボール(地球)が人々の手から手へと渡った。(中野さん提供)
西村昔、「国の寿命は150年くらいだ」という話を聞いたことがあります。150年もあれば必ず国も変わる。だとしたら、この50年を3コーナーあるうちの1コーナー目の終わりということになりますよね。じゃあ、あと2コーナーで大きく変わることを思い描きつつ「この100年で何をするのか」を考えるのもいいなと思いました。
中野未来をつくるという意味では「Emerging Future」というのは非常に賛成なのですが、自分を外に置いた予測のような未来論はつまらないなとも思っていて。どちらかといえば、今やっていることが自ずと未来を生むと思って、目の前のことを一つずつやりつづけて、その積み重ねが違う未来をつくっていくんだと思っています。流れのままに「『今ここ』を一所懸命やっていたら思わぬ未来が開けるでしょう」という感覚があって。
ジョン・レノンの『Imagine』の歌詞に「夢を見ている人だと言われるかもしれないけれど、僕は一人じゃないし、いつかみんなが仲間に加わって世界はひとつになる」というフレーズがありますが、僕もそういうつもりでやってきたし、夢を見る人って大事だなとずっと思っています。
西村僕は今日、中野さんの人生史を伺いながら、その積み重ねの上に今の2021年があるなと感じていました。僕が登場するのは、その途中からなんですよね。自分の関わっているところだけをみると10年ちょっとなのですが、そのスタート地点までにものすごい変化があったんだなと思いました。だから、やっぱり50年ぐらいで次の何かがあるというくらいの感覚で、ゆっくり行こうと思います。
 この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/
この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/
取材の最後は、中野さんがピアノを弾きながら「Imagine」を歌ってくださいました。
インタビューの前半は、中野さんの人生と中野さんが生きてきた時代について、ただただ耳を傾ける時間。オンラインだったけど、焚き火を囲んで長老のお話を聴くような感覚がありました。聴いている西村さんも「自分が何歳のときだろう」と重ねていたようで、ふたりの間で何か大切なものが受け渡されていく現場に立ち会っているようでもありました。
後半は、人と人が話す場をつくってきたふたりの対話がはじまり、特に「ディスカッションとダイアログは何が違うのか」を語り合うシーンは、このふたりの間だからこそ生まれる言葉があふれてくる瞬間だったと思います。そして、このようなダイアログが行われていることこそが、わたしにとっては「希望」に思われました。
というわけで、超重量級の幕開けになった「時代にとって大切な問いを問う シーズン2」。次回はエール株式会社 取締役の篠田真貴子さんへのインタビューをお届けします。どうぞ楽しみに待っていてください。